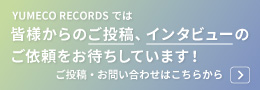走馬灯の様な11月が終わり、いよいよ年の瀬が襲ってきた。
ささやかな抵抗として暖房を付けずに、ブルースとうずくまる黄昏より、愛を込めて。
どうやらこの連載、次回が最終回の様です。
毎回タイトルを付ける時に「●●回」って書いているのだから、気付いてなかった訳もないのだけれど。でもまあ、流石に11回と書くともう、素通りも出来まい。とはいえ、こういうセンチメンタルな書出しすらもこの連載の通常運転だと思っているので、あと少し、よろしくどうぞお付き合いください。
冒頭にも書いたけれど、11月は音楽に関わるようになってからの私の日々の、ハイライトの様なひと月でした。バンドを愛し、イベンターとして活動をする友人の企画にやっと行けたこと。そこでまた、新しいバンドとの出会いがあったこと。この連載でもお馴染みのThe cold tommyとThe Doggy Paddleの対バンがあったこと。そこで、それぞれのバンドと“これから”の話ができたこと。名古屋の「しゃちほこロック」で担当しているバンドがコンテストで勝ち残って、東京に来たこと。結果こそ悔しいものだったけれど、彼らからもまた、興味深い未来の話が聞けたこと。「年末だから、節目だから、一年を振り返りましょう」なんて風潮は余計なお世話で好きじゃないし、ロックンローラーたるもの、常に前を向いて転がり続けていく所存だけれど、つい一歩ずつ後方確認してしまう質でもある。だから今、その通ってきた道のあちこちに、色んなミュージシャンの顔や言葉や音楽が浮かび上がるのを見て、柄にもなく、「良い一年だった」なんて台詞を言ってしまいそうになっています。
それに、ちょっと運命的な出来事もありまして。
先月、The Cheseraseraのアルバム『YES』とa flood of circleのシングル『花』には通ずるものがある、という話を書きましたが、偶然にもこの2バンドのライヴレポートを担当して参りました。The Cheseraseraの自主企画ファイナルと、a flood of circleの対バンツアーの名古屋公演。しかも先月に書いた順番通りに、2日連続なあたりも、やはり何かの縁を感じてしまう。そんな訳で、ひとりエモーショナルに感極まって眠れず、フラッドのライヴ後、名古屋のホテルで原稿を書きながら朝を迎えました。朝日でも浴びようと、冷えた指先をこすりながら、重たいカーテンを開けた時、目にした朝の街に、ふっとある曲が浮かんだ。それは前日のThe Cheseraseraの自主企画で聴いたGLIM SPANKYの「大人になったら」。(因みに下の写真はその時のもの)

GLIM SPANKYは松尾レミと亀本寛貴の2人から成るロックユニット。彼らの音楽に出会ったのは、今から一年以上前。松尾レミのハスキーヴォイスとドスンと重たいブルースが、みぞおちに入った。彼らのメジャーデビュー作「焦燥」だった。あの衝撃は未だに忘れない。
語弊を恐れずに言うと、10代の頃から、私の中でロックとは、好きか嫌いかの対象ではなかった。もちろん、ロックは好きだ。けれども“好き”である以上に、“必要”だったのだ。学校に行くとき、勉強をするとき、満員の通勤電車の中、病めるときも、健やかなるときも。いつも、ロックと一緒にいた。イヤホンの中のロックスターは、いつでも私のヒーローだった。でも、所詮、音楽なんてクラスの子、会社の同僚からしてみれば、ただの娯楽のひとつだろう。酸素がなければ死んじゃうけど、音楽がなくなったってケーキを食べればいいじゃない。そんなところでしょう。だからGLIM SPANKYの「大人になったら」を聴いた時には、驚いた。〈こんなロックは知らない 要らない 聴かない君が/上手に世間を渡っていくけど/聴こえているかい この世の全ては/大人になったら 解るのかい〉という一節がある。〈こんなロック〉を〈知らない〉だけでも〈聴かない〉だけでもなく、〈要らない〉と歌う。ああ、これはロックが“必要”なひとの書いた歌だ。そう思ったら、無性に泣いてしまいたくなった。多分私はずっと、こんなロックに出会いたかったのだろう。
この曲は、松尾レミが大学生3年生の頃に作ったものだと言う。進路に迷う中、自らは音楽の道を選びながらも、夢を諦める者、そのどちらも選べずに苦悩する者を目の当たりにしてきた。しかし〈大人〉に対する反発を歌いながらも、この曲は決して不貞腐れたブルースではない。松尾レミのアコースティックギターの音色はあたたかく、亀本寛貴のエレキの音に涙腺が緩む。そして、サビで先程の一節が歌われる。そこにあるのは青春時代への確かな敬意と、自らが生み出すロックへの信頼。私は、こんなロックがこのご時世に、しかも20代前半の若者によって生み出されたことが、たまらなく嬉しい。
彼らが上京したての頃に出来たという「夜風の街」では〈靄のかかった歌は、東京では唄えない/君の作った歌は、東京では流行らない〉という。私の中でロックというのは、常に輝いているものではないし、心地よいだけの存在でもない。どんよりと曇っていたり、錆びて軋んだり、見て見ぬふりをしていた気持ちの奥底を暴かれたり、強すぎる抱擁の様だったり。正直、ちょっとやっかいな存在だ。だがしかし、人間って多かれ少なかれ、皆面倒くささを抱えているし、それが味なんだと思う。そしてそういう人間臭さを、精一杯格好つけてさらけ出すのが、ロックなのだと思っている。けれども、なんだか最近、そういう生臭い音楽は流行りじゃないらしい。聴いて気持ち良く体を揺らしたり、なんだかお洒落な気持ちになるような、音楽がもてはやされている。音楽に、快感が求められる時代だ。確かに、疲れ切った頭に、さらに誰かが歌う苦悩の歌を聴くなんて、もしかしたら正気の沙汰ではないのかもしれない。
だけど。「やめとけばいいのに」って笑われたって、私はこの先もずっとロックを聴くだろう。そして、どうしようもなく胸が詰まる黄昏時にはいつも、彼女のかすれた声が寄り添うだろう。そうしたら、今度はそっとあの歌を口ずさんでみようと思う。
 イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。『MUSICA』鹿野淳主宰「音小屋」卒。鹿野氏、柴那典氏に師事。ちなみにライヴレポート、The Cheseraseraは「NEXUS」、a flood of circleは「しゃちほこロック」をチェックしていただければと思います。先日、革ジャンを着て革ジャンについての記事を書いた私ですが、実はレトロな服装も大好きで、GLIM SPANKYのレミさんのファッションをこっそりお手本にしています。可愛いんです、いつも。ほんとに。
イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。『MUSICA』鹿野淳主宰「音小屋」卒。鹿野氏、柴那典氏に師事。ちなみにライヴレポート、The Cheseraseraは「NEXUS」、a flood of circleは「しゃちほこロック」をチェックしていただければと思います。先日、革ジャンを着て革ジャンについての記事を書いた私ですが、実はレトロな服装も大好きで、GLIM SPANKYのレミさんのファッションをこっそりお手本にしています。可愛いんです、いつも。ほんとに。第10回「ロックンローラーよ、汝の過去を愛し、来たるべき未来を抱きしめろ」
第9回「ロックンロール対談:イシイマコト(ARIZONA)×村上達郎(Outside dandy)×恵守佑太(The Doggy Paddle)」
第8回「ケレンロックのすゝめ」
第7回「男心と、曇り空」
第6回「The cold tommy『FLASHBACK BUG』インタビュー」
第5回「平成の流し、世にはばかる」
第4回「ロックンロールの神様に踊らされて」
第3回「愛しき遠吠えのロックンロール」
第2回「The cold tommy解体新書的インタビュー」
第1回「やめられないから愛してる」