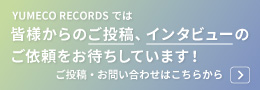どうも、今年もまた暗闇の中からこんにちは。
どうも、今年もまた暗闇の中からこんにちは。
2014年も、面白い映画がたくさんありました。今年は100本くらい観ましたが、その中でも特に印象に残っているものを、ご紹介させていただきます。観た順にバーッと挙げますね。
『ザ・イースト』(監督:ザル・バトマングリ)
エコ・テロリストたちの話。主演女優でありながら脚本、製作にも参加している才媛、ブリット・マーリングの名は覚えておいたほうがいいと思います。超エモーショナルな映画だった。
『メイジーの瞳』(監督:スコット・マクギー&デビッド・シーゲル)
離婚した両親の間を行き来する女の子の話。『ザ・イースト』にも出ているアレクサンダー・スカルスガルドの優男ぶり。メイジー役のオナタ・アプリールちゃんが可愛すぎる!
『抱きしめたい ‐真実の物語‐』(監督:塩田明彦)
実際にあった話を元にした北川景子主演の「難病もの」と聞いて侮るなかれ。天才・塩田監督、完全復活。全シーン分析したいほど映画的な技巧に溢れている。錦戸君も良かったな。
『劇場版テレクラキャノンボール2013』(監督:カンパニー松尾)
今年上半期の話題をさらった問題作。決して万人向けの作品とは思わない、というか別にオススメはしないけど、この映画を観る前/観た後では確実に何かが変わる…そんな一本。
『ダラス・バイヤーズクラブ』(監督:ジャン・マルク・ヴァレ)
俺たちのマコノヒーがほとんど別人になって熱演。パートナー役のドラァグ・クイーンを演じるジャレット・レトも良かったな。『ウルフ・オブ~』もあったし、今年はマコノヒーの年だった。
『ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅』(監督:アレクサンダー・ペイン)
アレクサンダー・ペインにハズレ無し。決して若くはない息子と父のロードムービー。こういうのが沁みる歳になりました。全編モノクロームの映像は、どことなく小津安二郎的でもある。
『アデル、ブルーは熱い色』(監督:アブデラティフ・ケシシュ)
惹かれ合う女の子たちのむき出しのパッション。センセーションで語られることが多い映画だけど、むしろ普遍的な何かを描いた一本として観るべきかと。実は社会的な映画だしね。
『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』(監督:ルッソ兄弟)
基本マーベルものには反応の鈍いワタクシですが、これは最高に良かった! なかなかどうして、実はポリティカル・スリラーな一本。っていうか、このルッソ兄弟って何者だよ!
『プリズナーズ』(監督:ドゥニ・ヴィルヌーヴ)
今年最大の発見と言えば、やはりカナダの映画監督ドゥニ・ヴィルヌーヴでしょう。もっと多くの人に観られるべき。彼の前作、『複製された男』も最高にスタイリッシュでカッコ良かった。
『罪の手ざわり』(監督:ジャ・ジャンクー)
中国「第六世代」の旗手、ジャ・ジャンクー6年ぶりの新作。実在する4つの事件をモチーフに、現代中国の「闇」をリリカルに描いた秀作。彼にしてはわかりやすい一本ではないかと。
『インサイド・ルーウィン・デイヴィス』(監督:コーエン兄弟)
画面のトーンをはじめ、映画のルックとしては地味だし、物語の起伏も弱いけど、ジワジワと沁み入るように好きになった一本。一応、音楽映画でもある。とりあえず、猫が超可愛い。
『ぼくたちの家族』(監督:石井裕也)
これもいわゆる「難病もの」だけど、それによって浮かび上がる家族の「秘密」という意味では山田太一的かも。実はリアリズムの映画です。妻夫木・池松の兄弟が良かったです。
『物語る私たち』(監督:サラ・ポーリー)
女優サラ・ポーリーの個人的な家族の話が、やがて予想外の結論に…というか、それを虚実入り混ぜながら「物語る」、サラ・ポーリーの監督としての手腕と才覚に脱帽。すごいわ。
『FORMA』(監督:坂本あゆみ)
今年映画ファンを最も震撼させた一本。観る者/観られる者、映っているもの/映っていないもの、など緻密かつストイックに設計された画面作りに、鬼気迫る才能を感じました。
『6才のボクが、大人になるまで。』(監督:リチャード・リンクレイター)
「ビフォア」シリーズでお馴染みリンクレイターが、それ以上の年月をかけて仕込んでいた、ある種「狂気」の一本。ある種『北の国から』をダイジェストで一気観するような濃密さ。
『ジャージー・ボーイズ』(監督:クリント・イーストウッド)
巨匠イーストウッドが、人気ミュージカルを完全映画化。これがスゴイ良かった…淡々としたタッチが、むしろエモーションを増幅させるという匠の技。音楽映画としても最高の一本。
『イコライザー』(監督:アントワーン・フークア)
ワケアリな主人公が、ある事件をきっかけに禁断の過去を解き放つ娯楽アクション大作。とにかくデンゼルが強すぎて最高。映画はかくあるべしというひとつのお手本のような作品。
『インターステラー』(監督:クリストファー・ノーラン)
『2001年宇宙の旅』への回答なんて見る向きもありますが、そこはノーラン。最終的にはエモーションでグイグイ引っ張ってゆく、ある種力技の一本。個人的には今年のベストです。
『フューリー』(監督:デヴィッド・エアー)
第二次大戦末期の戦車戦を、ほとんどドキュメンタリーのように描いた映画。謎の食事シーンをはじめ、何というか異形の戦争映画です。観終えた後、どっと疲れる体験型の一本。
『ゴーン・ガール』(監督:デヴィッド・フィンチャー)
最後に登場した真打ち。心技体、すべての面において本作が世界最高峰というのに異論はありません。まるで海外ドラマのような面白さ。まあ、そこが良くも悪くもありなんだけど。
ということで20本。この中で、さらに個人的に強く印象に残ったものを挙げるなら、『インターステラー』、『ジャージー・ボーイズ』、『6才のボクが大人になるまで。』、『物語る私たち』、『メイジーの瞳』の5本あたりになるわけですが、その並びを見るにつけ、ひとつのキーワードが浮かびあがって来るのです。それは「エモーション」。観る者の「感情」をどれだけ強く揺さぶることができるのか。
それは映画に限らず、多くのエンターテインメントにとって至極命題ですが、映画には他のメディアと異なる特性があるのです。それは「時間」を自在に操ることができるということ。それをリアルに刻み込もうとした実験作『6才のボク~』、バンドの結成から成功、そして…という「時間」を駆け足で描いてみせた『ジャージー・ボーイズ』、相対性理論を持ち出して、最後は「時間」という概念すら超越してしまった『インターステラー』など、それらの映画を観るにつけ、「時間」という概念は、我々の「感情」に強く訴えかける何かがあるのではないかと思うわけです。
あと、上記20本の中で、とりわけ多く扱われている題材としての「家族」。『メイジーの瞳』、『ネブラスカ』、『プリズナーズ』、『ぼくたちの家族』、『物語る私たち』、そして『インターステラー』。全部家族の物語と言って良いでしょう。といってもこれは、いわゆる「血」をめぐる問題ではないというのが重要であって……そう、さらに「疑似家族」というテーマまで押し広げてみれば、『ザ・イースト』、『テレクラキャノンボール』、『ジャージー・ボーイズ』、『フューリー』など、ほとんどの映画がすっぽり当てはまってしまうわけなんです。
その中心に何があるかと問われれば、それはやはり「時間」だと思うんですよね。ともに過ごした「時間」。その意味で「家族」というテーマが筆頭に上がって来るのもよくわかる話であって……「血」ではなく「時間」。なんだか昨年の映画『そして父になる』が提示したテーマみたいになってしまいましたが、「感情」を喚起させるものとしての「時間」――それは「体験」と言ってもいいのかもしれないけど――について、考えさせられることの多い一年だったように思います。それが個人的な嗜好なのか、時代的なトレンドなのかは定かでありませんが、とりあえず2014年の年末、ワタクシはそんなふうに感じたということをここに記して、本稿を終わりにしたいと思います。やっぱ映画って超面白いわ。
むぎくら・まさき●LIGHTER/WRITER インタビューとかする人。音楽、映画、文学、その他。基本フットボールの奴隷。