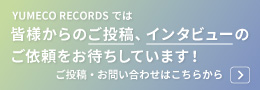好きなものに正直に、新しい「かわいい」を生み出してきた女性たちが主人公の物語「交差点のヒロイン」。
「ゴーストライターならぬ、エンジェルライター」がコンセプト。憑依するというより、守護天使のように、その人に取材し、共感をもって、物語を書きます。

今回のヒロインは、イラストレーターの田村セツコさん。
1938年に生まれ、1950年代後半より少女雑誌で挿絵やファッションページを手がけ、
『りぼん』『なかよし』『いちご新聞』などで、かわいいファッションやライフスタイルを提案する連載が一世を風靡。グッズなども当時の女の子たちの人気アイテムとなりました。
今も現役で精力的に活動を続け、その“かわいい”イラストと“おちゃめ”な生き方が、さまざまな世代の女性たちを魅了しています。
少女時代、駆け出しの時代、イラストレーターとして活躍を始めた時代、そして現在……4回にわたって、田村セツコさんの物語をお届けします。
第1話 郵便屋さん、ありがとう
第2話 苦労してこそヒロイン
▶︎第3話 締め切りが恋人
最終話 ブルーとバラ色のワンダーランド

セツコが会社を辞めて、もう1年が過ぎようとしていた。小さなカットを描いて、あとは自分の時間ばかりの、変わらない毎日。いつかきっと、私の描いた女の子が大きく雑誌に載る日がくる……そう自分に言い聞かせて、締め切りをきっちり守り、スケッチブックとにらめっこ。
その日、日課のスケッチをしているセツコの部屋で、電話のベルが鳴った。
「田村さん、お仕事のご相談なんですが……」
――また捨てカットかしら。もう飾り枠はお手のもの。出前迅速、なんでもご要望におこたえしますよ。
「はい、どのようなカットでしょう?」
いつものように返すセツコ。電話の向こうで、あわただしい声がする。
「それが……今度の『少女クラブ』の別冊に掲載されるユーモア小説の挿絵なんですが、担当の先生が急病になられまして、代役を探しているんです。締め切り、明日なんですが」
「えっ?」
いろんな情報が一気に入ってきて、セツコは混乱する。少女クラブ。ユーモア小説。画家が急病。締め切りが明日。それって――
「田村さん、描いていただけませんか?」
数秒のうちに、セツコはすべてを理解した。
「描かせていただきます」
助かります!と受話器のむこうの声を聞くやいなや、セツコは紙を机に広げる。
こんな仕事、初めて。
たくさん勉強してきたでしょう。セツコは自分に言い聞かせる。裸の女の人をデッサンしたり、流行歌を聴いてイメージをふくらませたり、映画の中の女の子を描いたり……。日本の少女たちに伝えたい女の子のすがたは、いつのまにかセツコの中で、ちゃんとできあがっていたのだった。
――デッサンに気をとられずに、顔はかわいく、よ。
夜を徹して、セツコは描いた。息さえとめるくらい集中して。
セツコが代役をつとめた、その号が発売になった次の日から、セツコの家のポストは速達で溢れかえった。
ぱんぱんに膨れた封筒を開けると、「『少女クラブ』の別冊を見ました」の文字。
――えっ?なんなのこれは。
便箋とともに、絵を描く指定の用紙が入っている。仕事の依頼だった。
それも、今までのような「捨てカット」ではなく、女の子の絵の。
「おちゃめな女の子を」
「ファッショナブルな女の子を」
「明るい性格の女の子を」
「例の調子で、お願いしますよ」
大きなリボン、しましまのソックス、ふくらんだスカート。チャーミングな笑顔の女の子。セツコ・スタイルの女の子が、ひとりで元気よく日本中を闊歩しているみたい。そんな女の子を、セツコ以外に描ける人はいなかった。
手紙は次から次へと届く。感動している暇もなく、締め切りの嵐。
手紙を確認すると、締め切りと、何色刷りかを電話で確認する。
「オフセットになります」
「はい、オフセットですね」
電話を切り、セツコは辞書をめくる。
――オフセットってなにかしら……あ、印刷用語なのね。
わかりません、できません、を言わないセツコに、仕事は大波のように押し寄せてくる。
寝るのも忘れて、セツコは絵を描きつづけた。ずっと描きたかった女の子。うまくいかないときもずっと味方でいてくれた、おちゃめな女の子。
セツコはいつのまにか、もう独りではなくなっていた。
会議室のテーブルの上に、料理ののったお皿とおやつのドリンクが並ぶ。
「なんだかパーティーみたいね」
「仕事の疲れもふっとぶわ」
「ああ、おなかすいた」
セツコと、小泉フサコ、藤沢トコの三人は、新人トリオの三人娘。同じ少女雑誌で挿絵を描く、仲良しの画家仲間だった。三人が出版社の会議室で急ぎのカットを描いていると、レストランから食事を取り寄せてもらえる。そんなおもてなしが、仕事の楽しみのひとつ。
三人は、連れ立って神保町の画材屋に行き、ケント紙や鉛筆をみんなで選んだりする。学生時代に戻ったようで、なんだか胸がおどる。
さんざん迷って、買えるのはケント紙一枚、鉛筆二本だけ。そんなセツコたちにも、画材店の店長さんは、いつもていねいにおじぎをして「ありがとうございます」と言ってくれる。
いつか売れっ子になって、紙も鉛筆も好きなだけ買えるようになっても、あの紳士の言葉をいつも忘れないでいよう。セツコは新しい鉛筆を削りながら、そう思う。
「セッちゃん、今月号の絵も大人気よ」
「ありがとうございますっ!」
少女雑誌の編集部は女性ばかり。趣味も合い、話をよくわかってくれる、面倒見のいい女性編集者たちだ。
――私よりも、編集者さんのほうが、「先生」だわ。
「セツコ先生」と書かれた郵便物を見るたびに、セツコは思う。先生だなんて呼ばれて、いい気になっちゃいけない。何でも教えてくれる編集者こそ、「先生」なのだと。
この、知的で辛抱強い、たいへんな仕事。作家や画家を相手に、励ましたり、待ったり、忙しいお仕事。
読者が自分の絵をどう思っているのか、セツコはあまり実感がなかった。読者のことを考える前に、担当さんのために、そして目の前の締め切りのために頑張る。そうやってひとつひとつ、仕事をこなしてゆく。
「セッちゃん、ちょっとそこで待っててくれる?」
担当さんにそう言われ、セツコは隅の椅子に座った。女性だらけの編集部の中、すみっこの席にはいつも、猫背のおじさんがいる。その人のことを、みんな「版下のおじさん」と呼んでいる。ページのタイトルや、見出しの文字を手書きする仕事だ。
――すごい。急いでいるのに、なんてていねいなのかしら。
にぎやかな部屋のすみっこでもくもくと筆を動かしている、版下のおじさんの仕事ぶりを、こうやって見ているのがセツコはとても好きなのだ。
細い筆でいろいろな書体の文字を書き、ホワイトで文字のすみずみを修正して仕上げてゆく。
雑誌に名前も載らない、版下のおじさん。この人がいるから、少女雑誌はかわいくなる。セツコは感心のため息をつきながら、おじさんの手もとを見つめる。
締め切りは絶対守ると決めたセツコは、どんなに急な仕事でも、少し体調が悪くても、雨の日でも嵐でも、締め切りまでに原稿を仕上げて編集部に届ける。チャンスをくれた松本先生の耳に、悪いうわさが入るようなことがあってはいけない、その一心なのだ。
夜でも原稿を受け取ってくれる夜間受付の職員さんとは、セツコはすっかり顔なじみになっていた。
「セッちゃん、なにしてるの?」
夜間受付に原稿を渡したセツコが振り向くと、社員の男の人たちが、笑いながら階段を降りてきたところだった。
「今日はクリスマスイブだよ」
「えっ?」
そういえば、街はいつもより浮かれている感じ。ケーキの箱を抱えている、お父さんらしき人や、おもちゃ屋さんの袋を持った子ども、寄り添う恋人たち。
セツコの予定はというと、今日も変わらず、原稿を描いて、届けることだけ。
――なんだか私、舞踏会に行けないシンデレラみたい?
そう思って、ふふっと笑う。セツコも今は20代後半。結婚しないの、と編集さんに聞かれることもある。
ひとつのことを仕上げてからしか次のことに取りかかれないセツコにとっては、目の前にある仕事が優先順位第一位。締め切りがいつも一緒なの……。
結婚のチャンスがあるとしても、仕事と結婚の両立は、できるものなのかわからない。結婚なんてものは、いつか自然に決まるものなのかもしれない。
クリスマスイブの夜、ひとりで歩く神保町も、それはそれで素敵だわ。セツコはそう思った。
異変が起きたのは、それからまもない日のできごとだった。
視界が、急に白黒になった。意識が遠のいて、次に気がついたときには病院のベッドにいた。
「からだが悲鳴をあげています。休息が必要です」
お医者さんが言う。自律神経をやられたらしい。ジリツシンケイ? 初めて聞く単語に、セツコはさらにくらくらする。
ここ何年も、仕事だけに生きてきた。からだが置いてけぼりになっていたのだろう。
――タフじゃなきゃ、ヒロインはつとまらないっていうのに、情けないわ……。
何かを変えないと。そう思いながら、セツコの頭の中は、今も仕事のことでいっぱいだった。
「ヨーロッパ美術旅行?」
友達の家で、セツコの目はテーブルの上のチラシに釘付けになる。猪熊先生の研究所で仲良くなった、高木清さんという画家だった。
「よかったら、それ持っていっていいよ」
チラシに見入っているセツコに、高木さんが言う。それは、美術館だけをめぐるツアーの案内だった。
――これだわ。
ヨーロッパに行く。その考えが浮かんだとき、セツコの胸にぱあっと風が吹き込んできたような感じがした。
初めてのヨーロッパ旅行!セツコは迷わず、そのツアーに申し込んだ。
飛行機の窓から、地図みたいに小さくなっていくパステルカラーの東京を眺める。
新しいスケッチブックの、最初のページを開いて、セツコは鉛筆を走らせる。
「セツコのヨーロッパ日記」
世界中の美しいものが詰まった美術館。人生をたたえるようなシャンソン。モード雑誌の中の世界が待っている。
ケ・セラ・セラ、とつぶやいて、セツコは空に浮かぶ雲を見下ろしていた。

最終話「ブルーとバラ色のワンダーランド」は7月15日に更新予定です。お楽しみに!
 大石蘭●イラストレーター・文筆家:1990年生まれ。東京大学教養学部卒、東京大学大学院修了。在学中より雑誌『spoon.』などで執筆。伝記的エッセイ『上坂すみれ 思春期と装甲』や、自伝的短篇『そんなお洋服ばっかり着ていると、バカに見えるよ』などを手がけるほか、著書として自身の東大受験を描いたコミックエッセイ『妄想娘、東大をめざす』(幻冬舎)などを刊行。現在もイラスト、文章の執筆を中心に活動中。(photo=加藤アラタ)
大石蘭●イラストレーター・文筆家:1990年生まれ。東京大学教養学部卒、東京大学大学院修了。在学中より雑誌『spoon.』などで執筆。伝記的エッセイ『上坂すみれ 思春期と装甲』や、自伝的短篇『そんなお洋服ばっかり着ていると、バカに見えるよ』などを手がけるほか、著書として自身の東大受験を描いたコミックエッセイ『妄想娘、東大をめざす』(幻冬舎)などを刊行。現在もイラスト、文章の執筆を中心に活動中。(photo=加藤アラタ)■HP : http://oishiran.com
■ブログ : http://lineblog.me/oishiran/
■Twitter : @wireless_RAN