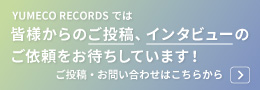某月某日:今日もまた暗闇の中へ。新宿バルト9で『風立ちぬ』。劇場で4分ヴァージョンの予告編を観たときから、すでに目元を潤ませ、これは完全にヤバイかもしれない……と思っていたけれど、実際問題、これは本当にヤバイ映画だった。これまでのジブリ作品とは明らかに異なる――しかし、他の誰でもない“宮崎駿”という刻印が押された圧倒的な作品世界。作画のダイナミズムと、それが生み出すエクスタシーという意味では常に感嘆しつつも、作品世界の中に時折顔を覗かせる送り手側の頑迷な思想と、それらを無視して無邪気に愛を注ぐ受け手のアンバランスな関係性がどうにも気になって、実はこれまであまりハマることのなかったジブリ映画だけど、今回は断然違った。この映画は素晴らしい。ここにあるのは、誤読のしようがない完全なる狂気だ。
 『風立ちぬ』は、零戦の設計者・堀越二郎の半生を描いた映画である。最初にそう聞いたとき、自分がどんな物語を思い浮かべたかは、もはや定かでないけれど、歴史を顧みるまでもなく、“残酷な形で砕け散った夢”として、それが悲劇になるであろうことは、きっと予想していたと思う。しかし、なぜ“風立ちぬ”なのか? 「風立ちぬ」とは、昭和初期に活躍した文学者・堀辰雄の短編小説である。「風立ちぬ、いざ生きめやも。」というポール・ヴァレリーの詩の一節をエピグラフとした悲恋の物語。堀辰雄と堀越二郎は、確かに同時代人であるけれど、両者の間に交流関係があったという記録はない。そう、宮崎駿自身が公言しているように、映画『風立ちぬ』とは、「実在した堀越二郎と同時代に生きた文学者堀辰雄をごちゃまぜにして、ひとりの主人公“二郎”に仕立てた」、彼の妄想の産物なのだ。
『風立ちぬ』は、零戦の設計者・堀越二郎の半生を描いた映画である。最初にそう聞いたとき、自分がどんな物語を思い浮かべたかは、もはや定かでないけれど、歴史を顧みるまでもなく、“残酷な形で砕け散った夢”として、それが悲劇になるであろうことは、きっと予想していたと思う。しかし、なぜ“風立ちぬ”なのか? 「風立ちぬ」とは、昭和初期に活躍した文学者・堀辰雄の短編小説である。「風立ちぬ、いざ生きめやも。」というポール・ヴァレリーの詩の一節をエピグラフとした悲恋の物語。堀辰雄と堀越二郎は、確かに同時代人であるけれど、両者の間に交流関係があったという記録はない。そう、宮崎駿自身が公言しているように、映画『風立ちぬ』とは、「実在した堀越二郎と同時代に生きた文学者堀辰雄をごちゃまぜにして、ひとりの主人公“二郎”に仕立てた」、彼の妄想の産物なのだ。
それだけではない。主人公“二郎”が夢の中で何度も邂逅するイタリア人設計技師、カプローニ(堀越と会ったという記録はない)。そして、“二郎”がヒロイン“菜穂子(これは堀辰雄の別の小説「菜穂子」の主人公の名前だ)”と運命の再開を果たす山荘に居合わせた謎のドイツ人、カストルプ(トーマス・マンの長編小説「魔の山」の主人公の名前だ)。この映画には、数多くの人物が召喚されている。なぜ、それらの人物が、登場しなければならないのか? その答えは、実に簡単だ。宮崎監督自身が、それらの人物や小説を愛しているからである。彼の偏愛の対象は、それ以外にも劇中の様々な箇所に見受けられる。青空や飛行機、そして緑豊かな自然風景といったお馴染みの描写はもとより、一般的にイメージされる緑色の“零戦”ではなく、その試作機であり“逆ガルウイング”という特徴的な主翼を持つ、九試単座戦闘機への偏愛。メッサーシュミットではなく、ユンカースのジュラルミン機体に注がれた偏愛。あるいは、タバコに対する偏愛。さらには、どこまでも優しい母、利発的な妹、薄幸の恋人といった、彼が理想とする女性たち。そう、彼が嫌いなものは、何ひとつ登場しないのだ。
 しかし、それら愛する「もの/こと」の集合体が、麗しいユートピアを形成するかというと、全然そうではない。恐らくそれが、この映画の何よりのポイントなのだろう。空を翔ける飛行機に魅せられ、自らもやがて設計技師となる主人公“二郎”が生み出す飛行機が戦争の道具となって行くように、ヒロインの健気な美しさが常に死と背中合わせにあるように、彼の偏愛の対象となるものは、どれもみな巨大な“矛盾”をその内側に抱えているのだ。それは、彼の天才性が最も露わになる作画面においてもしかり。映画の序盤に登場する未曾有の大震災イメージ。細やかなディテールと運動性をもって描き出されるそのシーンは、ある種トラウマ的な恐怖を観る者の心に植え付ける。または、墜落して無残な鉄塊となった飛行機の執拗に描き込まれたイメージ。自らの妄想をノーリミットで数珠つなぎにしながらも、彼のアニメ的リアリズムは、ときに容赦無いほど強烈かつ不穏なイメージを、観る者の心に与えてゆくのだった。
しかし、それら愛する「もの/こと」の集合体が、麗しいユートピアを形成するかというと、全然そうではない。恐らくそれが、この映画の何よりのポイントなのだろう。空を翔ける飛行機に魅せられ、自らもやがて設計技師となる主人公“二郎”が生み出す飛行機が戦争の道具となって行くように、ヒロインの健気な美しさが常に死と背中合わせにあるように、彼の偏愛の対象となるものは、どれもみな巨大な“矛盾”をその内側に抱えているのだ。それは、彼の天才性が最も露わになる作画面においてもしかり。映画の序盤に登場する未曾有の大震災イメージ。細やかなディテールと運動性をもって描き出されるそのシーンは、ある種トラウマ的な恐怖を観る者の心に植え付ける。または、墜落して無残な鉄塊となった飛行機の執拗に描き込まれたイメージ。自らの妄想をノーリミットで数珠つなぎにしながらも、彼のアニメ的リアリズムは、ときに容赦無いほど強烈かつ不穏なイメージを、観る者の心に与えてゆくのだった。
そして。映画の序盤、空翔ける飛行機の美しさに感動しまくった心は、やがてこの映画の全体が喚起する、様々な“矛盾”に打ち震えることになる。ときに、登場人物たちが織り成す物語とは違う場所――当時、日本という国が置かれていた情況(あるいは“矛盾”)そのものに思いを馳せるだけで、もう胸が締め付けられてしょうがないよ(奇しくも『華麗なるギャッツビー』と同時代だ)。プロットの盛り上がりとは全然関係無いところで、とめどなく溢れ出す涙、涙、涙。そして極めつけは、物語の時代背景とはまったく関係無い場所から鳴り響き、その“意味”を不思議とクロスオーバーさせてゆく、荒井由美の「ひこうき雲」だ。<あの子は死ぬ前も空を見ていたの/今はわからない/ほかの人にはわからない/あまりにも若すぎたとただ思うだけ/けれどしあわせ>。何だ、この歌詞は(汗)。
自らの人生を賭した“夢”はもろくも崩れ去り、その“夢”を支えてくれた最愛の人は失われた。ともすれば、発狂しかねないほどタフな情況の中、死者の口を借りて「生きねば。」と言わせてしまう、この圧倒的な妄想の自己完結力。そこに、未だかつてないほどの強度と迫力で、宮崎駿というアニメ作家の矜持を見たような気がした。そう、鉄の塊を空に飛ばそうという発想自体、すでに何らかの狂気をはらんでいると思うけど、考えてみれば“絵を動かす”、すなわち“アニメ”という表現も、実は相当な狂気をはらんでいる。映画『風立ちぬ』の“企画書”に、宮崎駿はこんなふうに記している。「夢は狂気をはらむ、その毒をかくしてはならない。美しすぎるものへのあこがれは、人生の罠でもある。美に傾く代償は少なくない。二郎はズタズタにひきさかれ、挫折し、設計者人生をたちきられる。それにもかかわらず、二郎は独創性と才能においてもっとも抜きんでていた人間である。それを描こうというのである」。そう、“二郎”とは、誰がどう考えても宮崎駿自身であり――だからこそ、この映画は素晴らしい。ここにあるのは、誤読のしようがない完全なる狂気だ。

むぎくら・まさき●LIGHTER/WRITER インタビューとかする人。音楽、映画、文学、その他。基本フットボールの奴隷。