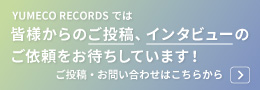某月某日:今日もまた暗闇の中へ。TOHOシネマズ渋谷で『華麗なるギャツビー』を3D鑑賞。“ギャツビー”と言えば、ロバート・レッドフォードが主演した1974年の映画『華麗なるギャツビー』が有名(マンダムの男性用化粧品ブランド“ギャツビー”は、この映画に由来しているんだぜ?)だけど、それはこの際いいのかな? “ギャツビー”と言えば、村上春樹が“生涯の一冊”と公言し、遂には自らの手で念願の“新訳”を手掛けたことでも知られる、スコット・フィッツジェラルドの小説『グレート・ギャツビー』の主人公――というか、アメリカ文学史に輝くその小説を、『ロミオ+ジュリエット』(1996)や『ムーラン・ルージュ』(2001)など、古典作品を絢爛豪華な一大スペクタクルとして現代によみがえらせてきた、オーストラリア人監督=バズ・ラーマンが3D技術を駆使して映画化したのが、この『華麗なるギャツビー』(2013)という次第。ちなみに、“ギャツビー”の映画化は、これで5回目だとか。
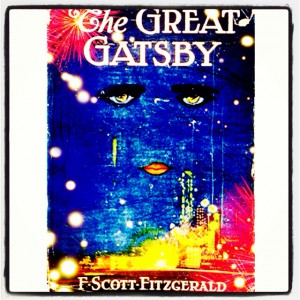 さて。舞台となるのは、1920年代のアメリカ――第一次世界大戦後の未曾有の好景気を背景に、享楽的な都市文化が勃興した“狂騒の20年代(ローリング・トゥエンティーズ)”です。フィッツジェラルドの言うところの“ジャズ・エイジ”ってやつですね。そんな時代にあって、お城のように巨大な自らの邸宅で、連日連夜、大規模なパーティを繰り広げる“謎の大金持ち”――それが、ジェイ・ギャツビーというわけです。プラダやティファニー、モエ・シャンドンらの協力のもと、細部まで凝りに凝った衣装&小道具とともに繰り広げられる狂騒の“宴”。爆音で流れるヒップホップ(!)。重力を無視して縦横に駆け回るカメラは、その3D演出も相まって、実に華々しい異世界へと観る者を誘って行きます。しかし、しばらくして、ようやくその“宴”の主宰者たるギャツビー(レオナルド・ディカプリオ)がスクリーンに登場し、グラスを掲げながら画面に向かってニッコリと、その“類まれな微笑み”を見せたとき、この映画の主役は、あくまでも“役者たち”であることに気づくのでした。
さて。舞台となるのは、1920年代のアメリカ――第一次世界大戦後の未曾有の好景気を背景に、享楽的な都市文化が勃興した“狂騒の20年代(ローリング・トゥエンティーズ)”です。フィッツジェラルドの言うところの“ジャズ・エイジ”ってやつですね。そんな時代にあって、お城のように巨大な自らの邸宅で、連日連夜、大規模なパーティを繰り広げる“謎の大金持ち”――それが、ジェイ・ギャツビーというわけです。プラダやティファニー、モエ・シャンドンらの協力のもと、細部まで凝りに凝った衣装&小道具とともに繰り広げられる狂騒の“宴”。爆音で流れるヒップホップ(!)。重力を無視して縦横に駆け回るカメラは、その3D演出も相まって、実に華々しい異世界へと観る者を誘って行きます。しかし、しばらくして、ようやくその“宴”の主宰者たるギャツビー(レオナルド・ディカプリオ)がスクリーンに登場し、グラスを掲げながら画面に向かってニッコリと、その“類まれな微笑み”を見せたとき、この映画の主役は、あくまでも“役者たち”であることに気づくのでした。
 周知の通り、『華麗なるギャツビー』とは、ある男の悲恋の物語です。失われた恋人を取り戻すため、その後あらゆる手段を使って築き上げた巨万の富を、惜しみなく浪費する孤高の主人公、ギャツビー。そして、今や上流階級の人妻となっているかつての恋人、デイジー。さらに、それらの事情を知った上で、ギャツビーの“よき友人(オールド・スポート)”であろうとするニック。それを、『ジャンゴ 繋がれざる者』で演じた大地主カルヴァン・キャンディの印象も記憶に新しいレオナルド・ディカプリオ、『17歳の肖像』で多感な女子学生を演じ、近作『ドライヴ』では夫のDVに悩まされる人妻を魅力的に演じていたキャリー・マリガン、そしてディカプリオとは『ボーイズ・ライフ』(1993)での共演以来、プライベートでも親友関係にあるというトビー・マグワイアが、それぞれ演じているのだから、これはもうズッパマリのキャスティングと言えるでしょう。
周知の通り、『華麗なるギャツビー』とは、ある男の悲恋の物語です。失われた恋人を取り戻すため、その後あらゆる手段を使って築き上げた巨万の富を、惜しみなく浪費する孤高の主人公、ギャツビー。そして、今や上流階級の人妻となっているかつての恋人、デイジー。さらに、それらの事情を知った上で、ギャツビーの“よき友人(オールド・スポート)”であろうとするニック。それを、『ジャンゴ 繋がれざる者』で演じた大地主カルヴァン・キャンディの印象も記憶に新しいレオナルド・ディカプリオ、『17歳の肖像』で多感な女子学生を演じ、近作『ドライヴ』では夫のDVに悩まされる人妻を魅力的に演じていたキャリー・マリガン、そしてディカプリオとは『ボーイズ・ライフ』(1993)での共演以来、プライベートでも親友関係にあるというトビー・マグワイアが、それぞれ演じているのだから、これはもうズッパマリのキャスティングと言えるでしょう。
映画は中盤、ギャツビーがニックの手助けのもと、デイジーと運命の再会をするあたりから、グッとトーンを変えて行きます。贅の限りを尽くした自らの邸宅にデイジーを招き入れ、その調度品の数々を嬉々として披露するギャツビー。そのあまりの趣味の良さに、思わず感嘆の声を上げるデイジー。ギャツビーは言います。「そりゃそうさ! この屋敷にあるものは、すべて君が好きなものでそろえたんだから!」。このシーンは、映画の中で最もロマンティックで美しいシーンであると同時に、とてもアイロニカルなシーンでもあるのです。悲しいかな、ギャツビーには、“中身”が無いのです。いくら外面を整えてみたところで、その中身はブランクなギャツビーという男。そんな彼のブランクな内面を、自らが内に抱える“空虚さ”と共振するように察知し、彼の信奉者であろうとするニック。そう、この物語は、いちばん欲しいものを決して手に入れることのできない者たち――ギャツビー、デイジー、ニック(そして、あるいはデイジーの夫たるトム)が織り成す、とてもパセティックな物語なのです。
正直、若い頃に手に取ったときは、さほど心動かされなかった小説『華麗なるギャツビー』。しかし、この映画を観た後、その時代に生きた人々――ギャツビー、デイジー、ニック、そして何よりも、その原作者であるフィッツジェラルドが、なぜ“失われた世代(ロスト・ジェネレーション)”と呼ばれたのか、少しだけわかったような気がしました。既成の価値観に絶望し、その中で生きる指針を失い、時代の迷い子となった、元祖(?)=ロスト・ジェネレーションの人々。物質的には満たされながら、それでもなおいちばん欲しいもの(その多くは“愛”でしょう)を手に入れることができない彼/彼女たち。無論、それは単に、僕自身が歳を取ったというだけの話かもしれません。そう、この映画のもうひとつのテーマとして、“過去は変えることができるのか?”という問題があります。誰よりも過去に縛られているが故に、その過去を執拗に塗り替えようとする“男”ギャツビー。その彼に、デイジーという“女”は無慈悲な現実を正直に突きつけるのです。「過去を変えることなどできないわ」。うーん、何か嫌な既視感のある話じゃございませんか、オールド・スポート(微笑)。
 さらにぶっちゃけると、バズ・ラーマンの映画は、見た目が華やかでサントラも結構充実してたりするので、割と話のタネにはなるものの、その内容については、ほとんど覚えてない……というか、結構何も残らないというのが、これまでのワタクシの印象でした。しかし、今回の映画に限っては、バズ・ラーマンならではの絢爛豪華な前半のパーティ・シーンと後半のシリアスな展開のコントラストが、文字通り視覚的にも“祭りの終わり感”や、ギャツビーの悲哀を浮き彫りにしているようで……要所要所グッと来たり、思わず目に涙を浮かべてしまったことを、ここに告白しておきます。『華麗なるギャツビー』――この映画を観終えた後、その“華麗なる”という言葉の裏側に感じるものとは? そして、本作の語り部であるニックが最後、“ギャツビー”という文字の上に、そっと“偉大なる(GREAT)”と書き添えた理由とは? 様々な反語表現が散りばめられたバズ・ラーマンの『華麗なるギャツビー』。これは思わぬ収穫だったというのが、個人的な感想でございます。
さらにぶっちゃけると、バズ・ラーマンの映画は、見た目が華やかでサントラも結構充実してたりするので、割と話のタネにはなるものの、その内容については、ほとんど覚えてない……というか、結構何も残らないというのが、これまでのワタクシの印象でした。しかし、今回の映画に限っては、バズ・ラーマンならではの絢爛豪華な前半のパーティ・シーンと後半のシリアスな展開のコントラストが、文字通り視覚的にも“祭りの終わり感”や、ギャツビーの悲哀を浮き彫りにしているようで……要所要所グッと来たり、思わず目に涙を浮かべてしまったことを、ここに告白しておきます。『華麗なるギャツビー』――この映画を観終えた後、その“華麗なる”という言葉の裏側に感じるものとは? そして、本作の語り部であるニックが最後、“ギャツビー”という文字の上に、そっと“偉大なる(GREAT)”と書き添えた理由とは? 様々な反語表現が散りばめられたバズ・ラーマンの『華麗なるギャツビー』。これは思わぬ収穫だったというのが、個人的な感想でございます。
むぎくら・まさき●LIGHTER/WRITER インタビューとかする人。音楽、映画、文学、その他。基本フットボールの奴隷。