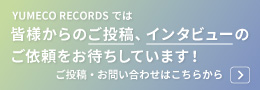某月某日:今日もまた暗闇の中へ。角川シネマ有楽町で、『シュガーマン 奇跡に愛された男』。アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞に輝いた直後ということもあって、平日にもかかわらず劇場は結構な客の入り。とはいえ、いわゆる“美談”の類なのかしらん?ってか、そもそもシュガーマンって誰よ?みたいな感じで、割かし平熱気味の温度でフラリ劇場に入ってみたワタクシ。しかし……これがビックリ、完全に予想の斜め上を行く、実に不思議なドキュメンタリー映画だったのです。
 1970年代初頭、本国アメリカで『COLD FACT』と『COMING FROM REALITY』という2枚のアルバムをリリースするもまったく売れず、音楽業界から静かに去って行った、デトロイトのシンガーソングライター、ロドリゲス。その彼の音楽が、1970年代末、なぜかほぼ地球の裏側に位置する南アフリカで熱烈な支持を獲得、以降20年にわたって聴き継がれているのだとか……。しかも、その事実をロドリゲス本人がまったく関知していないどころか、そもそもロドリゲスというミュージシャンが何者であるのか、南アフリカの人たちは、ほとんどよくわかってないという……そんなことって、あるのかしらん?
1970年代初頭、本国アメリカで『COLD FACT』と『COMING FROM REALITY』という2枚のアルバムをリリースするもまったく売れず、音楽業界から静かに去って行った、デトロイトのシンガーソングライター、ロドリゲス。その彼の音楽が、1970年代末、なぜかほぼ地球の裏側に位置する南アフリカで熱烈な支持を獲得、以降20年にわたって聴き継がれているのだとか……。しかも、その事実をロドリゲス本人がまったく関知していないどころか、そもそもロドリゲスというミュージシャンが何者であるのか、南アフリカの人たちは、ほとんどよくわかってないという……そんなことって、あるのかしらん?
や、実際問題、その類の話は結構ある気がします。日本でも大ヒットした「恋のマイアヒ」が、ルーマニアのポップ・グループ、O-Zoneの曲だなんて、最初のうちは誰も知らなかったわけで。当時の日本での盛り上がりについて、本人たちがどれだけ知っていたかは定かでないけれど、O-Zoneがいったいどんなグループで、どんな活動をしているのかなんて、未だによく知らないし。や、このたとえは良くないな。なんか微妙に古いし。「江南スタイル」の話にすれば良かったか。や、それも全然違う気がする。そう、ロドリゲスの話が奇妙なのは、何がきっかけだったのかよくわからないし、誰かが意図的に“仕掛けた”形跡も特に無いことなんですよね。むしろ、キーワードとなるのは、当時南アフリカで行われていた悪名高き人種隔離政策、“アパルトヘイト”だったりして。

「シュガーマン 急いでくれないか
こんな景色には もううんざりなんだ
青いコインをやるから 俺にまた
極彩色の夢を見せてくれ」
(“シュガーマン”)
「共感」というほど具体的なものではないし、そもそもコンテクストが結構異なっていたりするんだけど、とにかく響いてしまった……みたいな感覚。そう、これは震災後、個人的に感じたことだけど、目の前にある現実に積極的にコミットしようと意欲的に綴られた数々の歌(“絆”がどうしたとか、そういうやつ)も良いけれど、そうではない過去の歌のワンフレーズや、コンテクストの異なる楽曲の歌詞が、無闇に響いてしまうようなことが結構あってさ。「共感」と言うよりも、むしろ「共鳴」に近い感覚とでも言いましょうか。考えて理解する前に、なぜだか無性に響いてしまうような音楽体験。
「窓を開けて ニュースに耳を傾けようとしたが
聞こえてきたのは 権力のブルース ただそれだけ
怒れる若者たちの声に
やがて体制は崩壊するだろう
それが紛れもない冷たい現実」
(“ディス・イズ・ノット・ア・ソング、
イッツ・アン・アウトバースト:オア、ザ・エスタブリッシュメント・ブルース”)
想像するに、どうやらそんなふうにして、ロドリゲスの音楽は、南アフリカの若者たち(特にアパルトヘイト政策に内側から違和を感じていた白人の若者たち)の心に響いて行ったようなのです。アパルトヘイトという既存の体制(エスタブリッシュメント)に抗う、“反権力のテーマソング”としてのロドリゲス。それだけに、彼らの“ロドリゲス愛”は、相当なものがあります。なんてったって、自分たちの青春時代のテーマソングであり、1990年代にアパルトヘイト政策を撤廃させる、その原動力となった音楽なのだから。しかし、当時も今も依然としてロドリゲス自身の情報は、いっさい入って来ない。南アフリカで、こんなに愛されているにもかかわらず。っていうか、彼はそもそも生きているの?
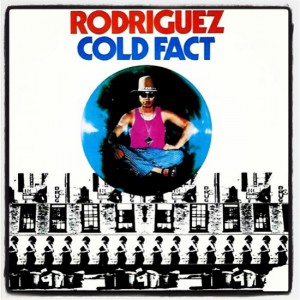
「今日あたり こっそり消えるつもりさ
おまえは成功のシンボルをとっておけばいい
俺は俺だけの幸せを探しに行くから
おまえは自分のペースや習慣を守ればいい
俺は砕け散った夢を修復しに行くから」
(“アイル・スリップ・アウェイ”)
やがて、南アフリカの人々の間で、ロドリゲスは“伝説化”されて行きます。「銃で頭を撃ち死亡した」、「ステージ上で焼身自殺した」、「獄中でヤク中のまま死亡した」など、悲劇的な最期のイメージとともに。そして、アパルトヘイトの時代も終了した1990年代半ば、南アフリカの音楽ジャーナリストとレコード店主の2人が意を決してロドリゲスの消息を調査し始めることから、このドキュメンタリー映画はスタートするのです。
しかし、この「調査」は、ある意味とてもスリリングなものとなります。何と言っても、この2人が調査を始めたのは、1996年頃の話。ロドリゲスが音楽業界を去ってから、すでに20年以上の月日が流れているのです。そりゃ、生きていてくれたら嬉しいけど、とんでもない「現実」にぶち当たる可能性も少なからずあるわけで。長年温めて来た「幻想」が、容赦ない「現実」によって打ち砕かれるみたいな光景は、もう何度も見て来たよ。開けずに済むなら、開けないほうが良い箱だってあるんです。そう、何よりも生きていてくれたら嬉しいし、そしてひとこと「ありがとう」と言えたなら、もうそれで十分じゃないか。
このドキュメンタリー映画が衝撃的だったのは、肥大した「幻想」がシビアな「現実」によって打ち砕かれる瞬間が記録されているから――ではなく、その「幻想」を凌駕してあまりある「現実」が、そこにスッと立ち現れるからです。その「現実」の中心にいるのは、無論ロドリゲスその人です。彼の一挙手一投足から滲み出る、圧倒的なオーラ。彼はいったい何者なのでしょうか? そして、音楽業界を去ってから、彼はいったいどんな人生を送って来たのでしょう? 「ギターは触っているけど、もう長いこと人前では歌ってないよ」。そんな発言とは裏腹に、彼は南アフリカ行きを快諾します。もちろん、ライヴをするために。そして――。
ロドリゲスをめぐる一連の“旅”を終えた後、「音楽は国境を超える!」とか「音楽は時空を超えて鳴り響く!」とか、激しく興奮しながら思わず口走りそうにもなるのですが……ロドリゲスというミュージシャンは、それ以上にひとつ重要なことを改めて思い起こさせてくれました。時空を超えて鳴り響く「音楽」を生み出すものは、果たして何なのかと。それは、紛れもなく「人間」です。「音楽」を――少なくとも彼の「音楽」を、彼の「人間性」や「哲学」、そして彼が辿って来た「人生」と切り離して考えることなど不可能です。ロドリゲスという人物は、それぐらいの説得力を持った「人間」であり「存在」なのでした。彼のような人を“アーティスト”と呼ぶのでしょう。市井に生きる、真の“アーティスト”としてのロドリゲス。
ちなみに、今年御年71歳となるロドリゲスは、現在も精力的に活動中。この映画がアカデミー賞に輝いたことを受けて、遂にようやく本国アメリカでもブレイクを果たしたようで、テレビ各局のトークショウへの出演から、数々のライヴ出演、そして先日行われた野外音楽フェス“コーチュラ”にも堂々の出演を果たすなど、大忙しの日々を送っているようです。そう、ロドリゲスの歌の中に、こんな一節があります。
「君の時間をありがとう
君も俺の時間にありがとうと言う
そしたらもう忘れてくれ」
(“ジェーン・S・ピディ”)
しかし、人々はロドリゲスの音楽を忘れてなどいなかった。その音楽が今、ロドリゲス自身の手によって、再び世界に向けて鳴らされようとしているのです。ワールド・イズ・ウェイティング・フォー・ユー、ロドリゲス! この感動を是非劇場でお確かめください。
むぎくら・まさき●LIGHTER/WRITER インタビューとかする人。音楽、映画、文学、その他。基本フットボールの奴隷。