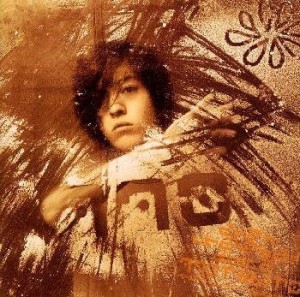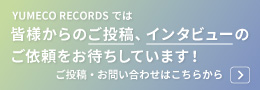このYUMECO RECORDSでは基本、来歴や個人的な感慨を寄せ、過去、くるり、LILLIES AND REMAINSの京都から産声を上げたバンドについて書かせて戴きました。なお、私的に想っていますのは、そのアーティストが好きだけで完結せずに、そのアーティストが影響を受けた色んな音楽、映画、書物、人物、場所などまで辿るのも楽しいという提案もあります。きっと独りでは何も生まれず、誰かは誰かの影響を受け、形成されてゆくからです。
今回は、七尾旅人さんを主題に僭越ながら書かせて戴こうと思うのですが、現在の彼はとてもアクチュアルな存在で、充分にポピュラリティを得ているのみならず、大きい意味性を持つ方ですが、過去にスピッツの「夢じゃない」に救われた、という言や初期のアシッドな様は伝わりにくさもあるかもしれず、それはおそらく時代が変わり、彼が変わったという言に収斂せずに、彼に時代が寄り添っていったとも感じます。つまり、徹底的に現場主義と、配信、ネット文化の双方を往来しながら、草の根で「歌う」ことを「撃たう」と記し、虚ろな目をした青年はハットと髭が似合う、優しくも峻厳な知性を持つ大人へと巡っていったのではないか、ということ。
七尾旅人さんは1979年8月の生まれですから、私自身と同世代、学年で言いますと、一つ彼の方が下と言うのもあり、時代感覚を皮膚に嚥下する痛点は似ていたような気が致します。オウム、宮台真司氏、小林よしのり氏、社会的ひきこもり、J-POP、小室系、自意識を巡る課題、90年代という今からしますと不気味な年代に思春期をおくったこと、そして、9.11、加速と混乱しながらの00年代、少しずつ息がしやすくなる世の中―こういった記号群を並べますと、上の世代の方からは「声の小さい世代」、下の世代からは「難渋な世代」、そんな見方も受けるかもしれず、ただ今、30代半ばの声が連なってきている実感はあります。それは相応に、語彙を持ってきたからかもしれず、小さい声に今は耳をそばだててくれる風潮が出来てきているという俯瞰も出来ます。
 1998年のデビュー・マキシ・シングル「オモヒデ オーヴァ ドライヴ」は端整な四曲、つまり、新しいシンガーソングライターとしての芽吹き、ニック・ドレイクやエリオット・スミスの持つ繊細ながらも華麗で儚い佇まいがあり、その後の展開を考えますと、ウェルメイドなアレンジメントが貫かれた曲が集まっていました。インナースリーヴには俯き、線の細く青白い彼の写真が載っており、手書きの歌詞、自在に刻印を避ける描写。例えば、一曲目に収められています「おもひで!おもひで!!」というアシッド・フォークな佳曲での歌詞カードの始まりはこう記されています。
1998年のデビュー・マキシ・シングル「オモヒデ オーヴァ ドライヴ」は端整な四曲、つまり、新しいシンガーソングライターとしての芽吹き、ニック・ドレイクやエリオット・スミスの持つ繊細ながらも華麗で儚い佇まいがあり、その後の展開を考えますと、ウェルメイドなアレンジメントが貫かれた曲が集まっていました。インナースリーヴには俯き、線の細く青白い彼の写真が載っており、手書きの歌詞、自在に刻印を避ける描写。例えば、一曲目に収められています「おもひで!おもひで!!」というアシッド・フォークな佳曲での歌詞カードの始まりはこう記されています。
① 揺れ動く君の胸を見ていた
② 学校さぼった
③ 工場の跡地 覚えた
④ 人形と人形の髪と人形のガラス玉
初期と言いましょうか、このシングルの二曲目の「八月」での〈プーティーウィッ?〉はSF作家のカート・ヴェネガットのノヴェルに出てくる小鳥の鳴き声であったり、ルイノン、告白ヴォーグ、コナツ、男娼ネリ、オーギュ、多くの造語のようで、色んな人物、キャラクター、イメージが行き交い、彼の脳内世界を垣間うかがえるようで、カオティックなまでに擬音、“吐息成分”と呼ぶ彼の歌唱まで世と渡り合うための音楽というよりも、生きるための痛みのような音楽―そんな印象があり、それはデビューフル・アルバムにしてdisc2と付され、雨に撃たう、99年の『雨に撃たえば…!disc2』での結実というのは重厚な作品に漂流します。「オモヒデ オーヴァ ドライヴ」にあったアシッド・フォークながら、端整に持ち堪えていた世界観はアルバム前の「おはよう…!ボンテェジ・サイボーグ」、「鉄曜日の夜→蘭曜日の朝」というマキシ・シングル二作で覆され、発声から多彩な音楽性が一気に加速しています。万華鏡のような、彼の愛するセリーヌ的な世界観、つまりは愛すべき背徳、SF的な色彩がダダ、シュールレアリスモ的に、描かれるような、誰しもが一旦は潜るかもしれない澁澤龍彦氏からサド、ランボオ、アンドレ・ブルトン、ルイ・アラゴンを抜けてのオートマティスム、そんな言葉を言葉そのものではなく、タイプライターマシーンを叩き割って、未予定の言葉群を連ねる行為性。
例えば、このアルバムの前半の仄暗さと後半のどこか光が差してくる間に挟まれた10分を越えるサイケデリックな「ガリバー2」という曲では、感情の振れ幅が見事に膨大な歌詞、独白、重ねられた彼自身の声とともに、顕現し、非・意味から意味までの文脈がしっかり視えもします。狭い部屋での無限大の妄想、内的世界観の追求は反転/錯綜と外界への思わぬリンクを示します。作家、表現者と呼ばれる人たちが一歩間違えれば、というのは危ない意味ではなく、誰もが「心当たりがありながらも、うまく表せない」鏡像でもあるかもしれず、ただ、そういう集合的無意識がメディア機能の増幅とともに、スター幻想をセットインしたならば、ニルヴァーナのカート・コバーンやマイケル・ジャクソンまで今でも世界中の人達を魅了し続け、救い続けているともいえるアーティストは幸せだったのか、懐疑も残ります。「ガリバー2」で、カットインされる「儚い」というフレーズ、一聴では全く掴めない詩世界はそれでも、このアルバムの感動的なラストへの橋を渡します。
“ポシェット”っていう部屋の中に居た。
“そこで僕は1302曲を書き、そんで43800本の煙草を吸い
5009回手を洗って、306回泣き、
64匹のアゲハに名前をつけ、2人愛し、5人憎み、
46回飛んで、3回ジグソーをあきらめ
(中略)
“ポシェット”と違う部屋。
病室? ぼんやりと...見える。
誰か....僕の顔を、のぞきこんでる。
僕に、そっとキスをする。
僕は、1回目の涙を流す。
誰だろう。すごく、優しい。
(「バニフォーおもちゃ工場の連中だよ!~露コナツ最初の日~」)
灯りが綺麗だった。
(「コーナー」)
なんだかうれしくなってしまう。
(「左腕☆ポエジー」)
当時、このアルバムを聴いていた私は、大学の今もあります主に少人数や再履修の方が集まるキャンパスで藻掻いていたときで、“1回目の涙”までを待つような季節でした。今でこそ、デフォルトな社会現象になっていますが、閉じた部屋へひきこもってゆくユースの心理が雪崩れながら、かろうじて学問や文学、色んな美しい何か、そこには音楽もあり、しがみつきながら、ポール・ニザン「アデン・アラビア」の誰もが模倣するような、「ぼくは二十歳だった。それがひとの一生の中でいちばん美しい年齢だなどとは誰にも言わせまい。」―そんなフレーズをポケットに入れていました。
その年齢部分がよく変えられて引用されているのは見受けられると思いますが、きっと華やかなばかりが青春や若さではないのだと思いますし、そのとき、眩かったキャンパス・ライフを謳歌していた同世代の人たちは今は何処に居るのか、分からないときはあります。例えば、今、「サーカスナイト」を歌い、生き残った彼や、その曲にリフト・アップされる世代を超えた感覚が不思議でもありながら、そのキャンパスにあった古びた地下の自販機は今は、どうなっているのだろう、そんなことも考えます。
宵闇が 僕らを包んで 天幕の中みたい
僕は冴えないピエロでも あなたはFearless Girl Circus Night
(「サーカスナイト」)
ロックンロールはエルヴィス・プレスリーのときから記号的に去って行った「Girl」(Blue Bird)を追い求める定めだったのかもしれず、そこにはロミオとジュリエットまでいかずとも、二人とは一人と一人の合わせ鏡であり、プラトンの言うように、球体、卵としてアダムとイヴは分かれなかったら、総ては幸せだったのか、私には永劫、分からないでしょうし、きっと分かったならば、音楽を聴くことすらしないのかもしれません。先日、15周年を迎えた中村一義さんの武道館公演を訪れたときも、全く性質は違うながらも、七尾旅人さんの来し方も考え、自身の「生」を反芻する瞬間がありました。
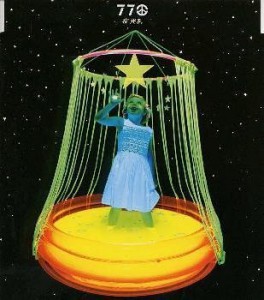 バレアリックにロックがダンスを希求していた、00年前後―それは、やはり何度書いても、アンダーワールドやケミカル・ブラザーズなどの音で一気に景色が変わってしまう、そんな進行形の感覚、ユーフォリアがあったからで、00年の「エンゼル・コール」、「夜、光る。」辺りの曲でのダンス・エレメントをまとい、浮遊するイメージは彼が完全に外へ出た、そして、その外で夜光塗料を撒き散らそうと考える無邪気な企て、光を探し始めた胎動があります。きっと、00年の時点、私も何処へでも、いや、何処かへ行けるそんな万能感は不安よりもあったのですが、その前景を翳めたのがいわゆる、2001年9月11日の景色でした。現実が映画やファンタジーを越える、しかも残酷な形で。何度も繰り返される映像越しに、どうにも行き場のない想いが往来していたのを今も想い出します。それは、また、10年代を経て、2011年、別次で得てしまう訳ですが、挫かれた希望的な何かの復興に時間を要するのはやむを得ない、そんな痛切な自省にも襲われました。
バレアリックにロックがダンスを希求していた、00年前後―それは、やはり何度書いても、アンダーワールドやケミカル・ブラザーズなどの音で一気に景色が変わってしまう、そんな進行形の感覚、ユーフォリアがあったからで、00年の「エンゼル・コール」、「夜、光る。」辺りの曲でのダンス・エレメントをまとい、浮遊するイメージは彼が完全に外へ出た、そして、その外で夜光塗料を撒き散らそうと考える無邪気な企て、光を探し始めた胎動があります。きっと、00年の時点、私も何処へでも、いや、何処かへ行けるそんな万能感は不安よりもあったのですが、その前景を翳めたのがいわゆる、2001年9月11日の景色でした。現実が映画やファンタジーを越える、しかも残酷な形で。何度も繰り返される映像越しに、どうにも行き場のない想いが往来していたのを今も想い出します。それは、また、10年代を経て、2011年、別次で得てしまう訳ですが、挫かれた希望的な何かの復興に時間を要するのはやむを得ない、そんな痛切な自省にも襲われました。
きっとここまでの話で、自分は自分、他人は他人、楽観的に、前進主義でいいじゃないか、という方も居ると思いますし、世代のズレ、感覚のズレはあると察しますが、敢えて偏向したイメージ輻射をさせていることを慮って戴ければ、と願います。メタ/ベタに意識や言葉は後から二次修正できる訳ですから、これがすべてとか部分とか、そういうのはなく、今、まさに、今、誰もが共有できる「それ」は「これ」ではないでしょう。
2002年のセカンド・アルバム『ヘヴンリィ・パンク:アダージョ』、ひきがたりに焦点を絞った翌年の『蜂雀(ハミングバード)』、とポップ・アーティストとして拓かれ、充実した作品を出しながら、また、うた、そのものを巡る前衛と実験がはかられた2004年のCD+DVDの「およそこの宇宙に存在する万物全てが【うた】であることの、最初の証明」を経ても、三枚組の規格外の9.11を巡る2007年の『911 FANTASIA』まで、00年代初頭の例のことのオブセッションが続く、それが01年~07年の時間差分をして過剰と言う向きもあるとしましても、やはり、背筋の通った音楽でした。
だからこそ、そこから、2009年に一気にポップ・フィールドへの地表化の契機となったやけのはらさんとのコラボレーション・シングルにして、新しい時代の「今夜はブギーバック」とも一部で言われました「Rollin’ Rollin’」に行けたような気もします。小沢健二さんがかつて唱えたアーバンソウルへの敬虔さは、別種の美しい形で継承され、あの七尾旅人さんの澄んだ声がスウィート・ソウル・ミュージックにして、明けない夜のためにレコードを回し続けることへの意思を押しました。
Rollin’ Rollin’ 回り続ける 運命に 運ばれて
Rollin’ Rollin’ 忘れたまんま 知らない場所まで 流されて
Rollin’ Rollin’ 回り続ける レコードに 運ばれて
Rollin’ Rollin’ わからないまんま ながくながく 流されて
そう
BABY OH BABY KEEP COMIN’ BACK
(「Rollin’ Rollin’」)
わからない、まま。初期、彼は世の中自体へのわからなさを抱えていたとしたら、音楽の不思議さのわからなさへと至ったような鮮やかなエレガンスに貫かれた視点。
―10年代、今の七尾旅人さんは十二分に誰もが語ってくれるような、御本人が一番、自覚的に動かれている想いがするのは私だけではないと信じたくもあり、新作が『リトルメロディ』と付され、誰でもが手に取れる内容に、間口になっているのは偶然ではなく、必然的な、美しさがあります。彼は基本、ずっと自分・対・世の中を歌ってきましたし、最近では「撃たう」が再び「歌う」に切り替わったここでは、日常の大切さ、さり気ないものへの意識を届けられる、さらに、その「うた」はみんなが口ずさめる、胸が締めつけられるものではないでしょうか。きっと明日にも音楽は鳴り響き続ける限り。
くちずさむたびに 僕は変われた いつか かなえてみせるって 小さなメロディ
これから僕ら やり直せるさ どんな壁も超えてゆけよ 小さなメロディ
いつか僕らが ここを離れても きっと誰かが口ずさむ 小さなメロディ
(「リトルメロディ」)
いつか、「誰も」がうたを忘れても、きっと「誰か」が口ずさむ、そういう希いを込めてこの原稿の筆を置きます。
まつうら・さとる●1979年生まれ、大阪府出身。好きな音楽と語義矛盾を感じ、音楽やそこに関わる文化や人が好きなのだと最近は考えてもいます。COOKIE SCENEなどをベースに多岐に渡る執筆活動を行ないつつ、基本、研究員、にして左岸派。ノンカフェインのお茶が好きです。近況として、東京にてこのサイトの主宰者たる上野さまに初めてお会いした印象は、絶対敵を作らない朗らかな鋭い知性とコーヒーとスイーツでライブに蓄える、流石のたたずまい、でした。