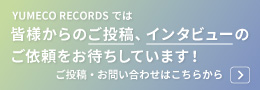一方的に夢を託したのは7年前のこと。
とある人から「最近気になるバンドは?」と尋ねられ、「そのバンドなら確か、今度対バンに出演する予定があった気がする」と数日後に代官山UNITへ連れて行ってもらった。そのバンドを仮に「A」とする。彼らはまだ若く、演奏がずば抜けて上手かったわけではない。だけど、鳴らす音の一つひとつが私には輝いて見えて、ステージ上のメンバーがとにかく楽しんでいること、彼ら自身が自分たちの音楽を愛していることがダイレクトに伝わってきた。音程がちょっとズレたときの「あちゃ~!」っていう感じまで出ちゃっているのが可笑しい。音楽に感情が全部乗っちゃっているところに無性にワクワクさせられた。
私は今、音楽ライターとして書くことを生業にしている。その頃はいわゆる駆け出しの時期で、心から「追いたい」と思えるような、キャリアを重ねるにつれて互いに切磋琢磨していけるような(あるいは、こちらが勝手に食らいつくことによって野心を焚きつけられるような)同世代のバンドを探していた。そしてあの日、Aのライブを観て「見つけた」と思った。同時に「このバンドが武道館に立つとき、私はそのライブのレポートを書く」「その日が来るまではせめてライターを辞めない」と誓った。飽き性で根性無しの自分を縛るための鎖を作った。
それは誰にも言わずに決めたことで、自分から何か働きかけたわけではないが、不思議なことにその後、Aとともに仕事をすることになった。今では、音源をリリースした際にはインタビューをさせてもらっているし、ツアーが開催された際にはライブレポートを書かせてもらっている。
かつての私にとっては趣味の一つだった「書く」という行為は今では仕事になっている。仕事をしていると、自分の正義と誰かの正義が衝突することがある。そうなったときには話し合いを重ね、それぞれにとっての譲れないポイントを探し、互いに納得できる落としどころを探すプロセスが必要になってくる。それは手間のかかる作業だ。だからこそ、感情のないロボットになってしまった方がいっそ楽なんじゃないかと思うことがある。惰性や手癖で作業してしまった方が、何かを諦めている状態から始まった方がいっそ楽なんじゃないかと思うことがある。だけど、彼らのライブを観るたびに思い出させられるのだ。ダメだよ、諦められないから、どうしても自分の言葉で語りたいと思ってしまったから、これを仕事にしたんじゃないか、と。ライブハウスをトーンアップさせるみたいなキラキラとした音色は、私にとっての灯台であり続けた。暗い海を彷徨っているときでも、その光を目指せば、自分の道を見失わずにいられた。
Aはまだ武道館でライブをしておらず、私の夢は叶っていない。しかし一度だけ、叶う前に、諦めてしまおうかと思ったことがある。昨年秋、自分がライターを目指すきっかけとなったバンドが、活動終了を発表したときのことだ。
人は大きなショックを受けると、往々にして言葉を失う。自分の心の内側で発生している感情の荒波のことを「名状しがたい」と言う。しかし私はそうならなかった。悲しくて虚しくて心は空っぽなのに、書くことがやめられない。肋骨を抜かれたみたいな感覚に襲われながらも、タイピングは止まらない。「もう書けないかもしれない」どころか「だからこそ書かなければならない」としか思えない。そういう境遇を選んだ自分、そういう生き物になることを選んだ自分の性(さが)を、私は恨んでいた。
私の人生を変えたバンドは、この世界にもういない。それでも私は、こうやって書くことを生業にしてしまえる。私の人生を変えたバンドは、新しいツアーにもう出発することがない。それでも私の内側からは、言葉がどくどくと溢れ出す。そのことに絶望していた。
奇しくも翌日はAのライブだった。先に書いたように私はライブハウスで観るAが好きだが、それでもさすがに今回ばかりは足が重い。とはいえこれは取材であり、仕事であり、「行きたくないから行きません」なんて言えるわけがない。だから行け。這ってでも行け。正直、開演するまでの時間が憂鬱だった。
しかし数分後、私は凝りもせずライブハウスに、ロックバンドに救われた。その日のライブを含む全国ツアーは、Aにとって重大な意味を持つツアーだった。事故に遭い、一時は生死を彷徨ったベーシストが復帰し、10ヶ月ぶりにメンバー4人がステージ揃う。そんなタイミングでのツアーだった。
セットリストの4曲目。未知に出会った瞬間の心のざわめきや、困難に直面したときの絶望、それらの先に待つ一生をかけて向き合おうと思えるものとの出会い――つまり人生を唄ったあの曲に、今の自分を重ねずにいられなかった。7年前と同じように、ステージから溢れ出すバンドの音は歓びを乱反射させている。まだライブの序盤なのに、というか仕事で来ているんだから本当は我慢したかったのに、ボロボロと涙がこぼれていた。「バンドは解散するし人は死ぬ。別れは絶対あるよ」「だから口を開けて唄うし、手術後のおぼつかない手でベースを弾くし、野生児のように叩くし、感情を露わにしてギターを弾く。みんなが生きてる!って思える瞬間、空間を作っていきたいです」「だから一緒に生きよう! 一緒に唄おうぜ、兄弟!」。MCでの一言一言がぐさぐさと刺さる。終演後に湧いたのはAに対する「やっぱり彼らはカッコいい」「私だって負けないぞ」という感情。ということは、あのときの審美眼はちゃんと正しかったのだろう。いろいろなものを乗り越えてスゲーカッコいい音楽を鳴らしているバンドと一緒に仕事している身なのだから、いろいろなものを乗り越えてスゲーカッコいい文章を書けるライターになろう。改めて、そう腹を決めた。
「ライブハウスは好きですか?」という質問に対し、手放しで「はい」とは答えられない。なぜなら「こんなに苦しい想いをするくらいなら、ライブハウスなんて知らなければよかった」と思ったことがあるからだ。しかし、私を崖の底から引っぱり上げてくれるのもまた、ライブハウスで音楽を鳴らすロックバンドである。今日に至るまでそんなことを何回も、何回も繰り返してきている。それらの経験が私という人間の大部分を構成している。
ライブとはその場に集まる人々、その空間に携わる人々の「今」の結晶であり、すべてはやがて過去になる。永遠なんて存在しない。現に、私の人生を変えたバンドは、この世界にもういない。もっと言うと、初めて行ったライブハウスも、その次に行ったライブハウスも、(コロナ禍によってではないが)だいぶ前に閉店した。
ならば、思い出も一緒に消えていってしまったのか? いや、そうではない。ライブハウスでの出来事は、その瞬間、心を揺り動かされた者の血や肉となり、人のなかで生き続けるのだ。
未来は不確かだし、特に今はライブハウスに行くことすら叶わない状況だ。しかし、あなたのなかにあるかげがえのない思い出は――心が一気に昂ったり、息を呑むほど驚いたり、そっと涙を流したり、人知れず感慨を噛み締めたその瞬間は――誰のどんな言葉にも侵されやしないはずだ。
だから今こそライブハウスの話をしよう。明日が楽しみだと笑いながら、眠りにつくことのできるその日まで。

 span style=”font-size: 120%;”>蜂須賀ちなみ●フリーランスのライター。学生時代に『音楽と人』へ寄稿したことをきっかけに活動開始。『ROCKIN’ON JAPAN』『Skream!』『SPICE』『リアルサウンド』などに寄稿。YUMECO RECORDSでは6~7年ほど前にBase Ball Bear、NICO Touches the Walls、[Champagne](現[Alexandros])のレビューを掲載していただきました。
span style=”font-size: 120%;”>蜂須賀ちなみ●フリーランスのライター。学生時代に『音楽と人』へ寄稿したことをきっかけに活動開始。『ROCKIN’ON JAPAN』『Skream!』『SPICE』『リアルサウンド』などに寄稿。YUMECO RECORDSでは6~7年ほど前にBase Ball Bear、NICO Touches the Walls、[Champagne](現[Alexandros])のレビューを掲載していただきました。