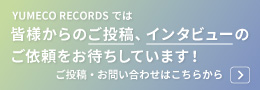GWも終わり、五月病が流行始める今日この頃。
皆様、如何お過ごしでしょうか。
ちょっと憂鬱な時期ですが、当連載は今月から本格始動!
今回はGOMESSさんというラッパーを迎えてお送りします。
自他共に認めるロックンロール好きが、なぜラッパーを?とお思いの方もいらっしゃることでしょう。お察しの通り、恥ずかしながら今まで聴いたラップと呼べる音楽はRHYMESTERくらいです……。しかし、そこでキーワードになるのが、今年度のテーマ「音楽」とそれにまつわる「カルチャー」。
ラッパーだけど、作家でもあり、哲学者でもある。
GOMESSさんから感じたのは、表現と人間に対する際限ない欲求でした。
■インタビュー「箱庭から見つめる終末と希望」――ラッパー:GOMESS
高校生ラップ選手権準優勝を機に注目を集めた1994年生まれの若きラッパー・GOMESS。彼は幼少の頃より自閉症と共に生きてきたことでも知られている。自らの生き様を歌った「人間失格」や「LIFE」ではかなり強烈な言葉が並ぶが、それは単なるセンセーションではなく、彼にとってのリアルでしかない。そんな生々しい叙述をする一方で、彼が雄弁なストーリーテラーであることを証明したのが、前・後篇2枚のアルバムと完結篇にあたる単独公演からなる連作『情景』だ。音楽、そして舞台表現を通して彼が描こうとしたのは『情景』という名のひとつの物語だった。今回のインタビューでは彼の表現者としてのスタンスを「ラップについて」「『情景』について」「終末について」の3部構成で浮き彫りにする。

phrase01:文系ラッパーはかく語りき
――最初にGOMESSさんの作品に触れたのはYouTubeで公開されていた「消滅」だったんですけど、その時にラッパーのイメージが覆されたというか……“この人文系だ!”って思ったんです。失礼ながら今まで“ラッパー=体育会系”みたいな勝手なイメージがありまして……。
「文系(笑)言葉はすごくこだわっているので嬉しいですね。でも国語はずっと苦手だったんです。文法って言葉の意味がまずわからないし、漢字も読めるけど全然書けなかったし。小説や詩集も読んだことがないんです」
――そうなんですか!?
「歌も音だけ聴いて歌詞カードは読まないし。フレーズ単位だったら“この言葉いいな”というのはあるんですけど。ストーリーがいいなって思ったことはあんまりないですね」
――確かに。ストーリーに完全に気付くのって歌詞カード読んだ時かもしれませんね。
「そうですね。でも歌詞カードを読む時って自分のペースで読めちゃうから。たとえばサビが流れていても、目は次を読んでいたり。実は歌詞を踏まえた上でサビは聴けてる訳ですよね」
――なるほど。そう考えるとフリースタイルのラップは即興だから、初めて耳にする詞をリアルタイムで理解させるワケじゃないですか。すごいことですよね。
「ラップの方が日常の言葉に近いからでしょうね。ラップって、歌として考えれば早口だけど、喋っていると思えばそんなに早口でもないんですよ」
――確かに。だからいわゆる“歌”として歌われる歌詞よりダイレクトに伝わってくるんですね。
「そうかもしれない。歌の言葉って本来もっと早く読めるのに、すごくゆっくりスクロールされていくからストーリーとして考えるのが難しいんじゃないかなって」
――うん、そうかもしれません。GOMESSさんはフリースタイルをする際、どんな風に言葉を紡いでいくんですか?
「喋るのと変わらないです。僕のフリースタイルは返事を貰わないことが多いので、一方的に話かけるだけですね。客は意識するけど、対象としては選んでないというか、相互関係じゃないから。だからラジオと変わらないんだけど、ラジオだとつなぎの言葉とかがあるじゃないですか。でも自分がラップをやる時は、無駄な言葉はあってはならない。ただのトークとの区別はそこでつけたいな、と思っていますね」
――MCではない、と。
「そうですね、MCとの違いが唯一あるとしたらそこですね。言葉一個手抜きしない。トークも手抜きしてる訳じゃないですけど、ひとつひとつの言葉に力を込めて、自分の中でしっかりと詞として成立させる。後から映像で観ても自分に対して“カッコイイ”と思いたいんですよ。“これホントに即興で作ったの?”というクオリティーを出せないとわざわざ即興でやる意味はないのかなって」
――最近アップされていた3分間の動画も即興ですよね。映像化する際に詞を文字にして載せているじゃないですか。それでも全く矛盾することなく、言葉が順序良く物語を描いていて驚きました。
「単純に、嘘ついてないのと作り話をしていないだけ。飛んだことを言ってるように見えるかわからないですけど、自分の中ではとてもシンプルで。ファンタジーではなく、現実的な話ばかりをしているんです。あの動画だと色がどうの、っていうフレーズが出てくるから空想や比喩表現のように見えるけど、自分の中ではシンプルに見たままを言っているからブレようがない」
――なるほど。そうやって目の前にあるものを表現していくフリースタイルがある一方で、『情景』という一連の作品についてはしっかりと世界を構築した上で表現している。これはかなり対極にある表現方法だと思うのですが、いかがでしょう?
「そうですね。『し』というセカンドアルバムの時に、既にこういうイメージのことをやろうとしたんですけど、それを改めて詰めていって。ようやくちゃんと一個の形として表現できたかなって思うのが今回の情景シリーズですね」
――なるほど。では『し』と『情景』のシリーズはある意味繫がっているんですね。
「その通り。『情景』って『し』の一番最後にある「箱庭」という曲のお話なんです。実は全部の作品が繫がっていて。『し』については、ファーストの最後の曲「笑えてた」と繫がっているんです。即興で作った曲なんですけど、笑えていることへの不安や肯定、それでも消えない葛藤を抱えながら苦しむ曲で。それを経て『し』は自分の事が信じられないという不安に陥っていくんです。それで最後“世界に飽きたから自分は箱庭の中に世界を作って壊すっていう遊びをする。それで僕は神様になるんだ”という「箱庭」で終わるんです。だから『情景』って、空想の世界の物語なんですよ」
phrase02:思考の箱庭を飛び出した“情景”の世界

――フリースタイルでなくとも、今までは「LIFE」や「人間失格」などご自身の生きざまを歌ったリアルな楽曲がGOMESSさんの特徴という印象でした。なぜここで空想の世界を描こうと思ったんですか?
「箱庭で遊んでいたのは小学生の頃なんですけど、それよりずっと前から頭の中で物語を作ってひとりで演技をするのが好きで。登場人物の名前も決めて、簡単なプロフィールを決めて、ビジュアルイメージも絵で描いて。で、物語の冒頭だけ作ってインプロビゼーションみたいな感じにひとりで劇をするっていうのを高校生になるまでやってたんです。親がいない時に、こっそり。それの延長線という気がしているから、あんまり新しいことをやった感じはないんですよ」
――“劇”という言葉が出ましたが、先日開催された『情景』シリーズの集大成となる単独公演ではGOMESSさん自身もステージ上で“舞台”と呼んでいたように、まさに“劇”でしたよね。
「そうですね。昔から遊んでいたことを、ちゃんと創作に活かせたのかな、と」
――ステージ上にはGOMESSさん以外にもたくさんの出演者がいて、ダンスとかポエトリーリーディング的な独白など、音楽以外の表現も盛り込まれていました。なぜ音楽だけでなく総合的エンターテイメントとして『情景』の世界を表現しようと思ったんですか。
「空想の話をしているのに、自分がステージの真ん中にマイクを持って客に向かっているのって変じゃない?って。普段のライヴではそうしますけど、そういう時は『情景』の曲はやらない。リアリティー100%じゃないからドヤ顔で“俺の曲”みたいにしたくないなって。自分で言葉は書いているけど、俺の話じゃないし。だから自分はずっとステージの端にスタンドを立てて、真ん中には行かなかった。変な話、あの日真ん中に立ったのって中尾有伽だけなんですよ」
――確かに、そう言われてみるとそうですね。
「『情景―後篇―』の主人公は中尾有伽なんですよ。PV含めビジュアルイメージも俺じゃなくて中尾有伽にしたかった。それで俺は端っこにいたい。空想の話をするにあたって自分は真ん中に立てないからどうしようかと思ったときに、彼女を真ん中にすることを思い立って。それが『情景―完結―』という舞台を作る一番のきっかけだったかもしれません」

――なるほど。小さい頃から続けていたひとり芝居に、初めて出演者が出来たってことですよね。
「そうなんですよ!いやあ、嬉しかったですね」
――出演者の方々には、表現について細かく指示を出したんですか?
「舞台上のポジションとかは細かい指示を書いた表を作ったりしていたんですけど、ニュアンスで伝えた部分も多かったです。例えばシャウトをしてくれた柴田匠(MINOR LEAGUE)さんには“あなただけは唯一取り乱して叫べる役だから、苦しくなって全員分叫んでほしいって”って伝えていました。あ、でも中尾有伽だけは「中尾は中尾らしく」って書いてあるだけなんですよ」
――ええ!?
「今回の舞台で喋っていいのは俺と中尾有伽だけと決めていて。彼女がひとりでずっと喋るシーンがあったと思いますが、リハーサルを一度もしていなくて。彼女はあれを全部あの場で言葉にしたんですよね」
――それが成り立つのも『情景』という作品が中尾さんから生まれているからですよね。
「そう。彼女が何をしてもハマるようにできてるんです。だから黙り込んでもいいし、泣いてもいいし、笑ってもいい。怖くなってステージから隠れちゃってもいい。ギターやマイクを壊してもいい。……入ったら出ててこれなくなるタイプだから、怪我だけはしないでほしいなって思ってましたけどね。翌日のTwitterを観たら、膝がアザだらけの写真がアップされていて」
――それほど激しくパフォーマンスをしていたってことですね。
「そうですね。即興で泣くところまでやって、泣き顔をさらした上で体を痛めつける。半分もうわざとだと思うんですけど、痛いっていう衝撃で自分の感情をバンと思いっきり前に出す。こういうことをしているの、僕以外に男女問わず見たことがなくて。だからこれをやれるやつをようやく見つけた、っていう嬉しさはありましたね」
――GOMESSさん自身も自分を痛めつけるようなパフォーマンスをされるんですか?
「僕の場合はマイクで首を絞める……とか。とにかく苦しい、痛い、悲しい、っていう想いを強く自分に与えて、つらい想いまでしないと出せないものを出したいんです」
――そうまでして表現したいという欲求というか、何がGOMESSさんをそこまで突き動かすのでしょうか。
「求められている以上のことをやりたい。そこまで言わなくていいよ、っていうところを言っちゃう人でいたい。年をとってもっと不自由になるのが見えるから、今のうちになるべく自由に発言しておきたいな、と。あとは縛られている人がかわいそうだなって。なんで我慢してるんだろう、って。それは優しさだったり臆病だったりすると思うんですけど。言っちゃえばいいのに……言えないんだったら逃げればいい。もちろん戦ってもいいんだけど。とにかくアクションを取れなくなっている人が多いから、それを体現したいなって」
――壊すことと、その先を魅せたいと。
「そうですね。でも変な話、僕は今ここでヤバいことはしないじゃないですか。あくまでそれをするのはステージ上だけで。でも僕は音楽やアーティストを観た時、自分もそうして……泣いたり取り乱したりしていいんだよなって思う瞬間があって。例えば相方を失ったミュージシャンが、その後のライヴで号泣しながらそいつと作った曲を歌う。そういう瞬間がすごく好きで。相方を失ってもまだやらなきゃいけないし、やりたいんだもんな、って。そういうときに沸き起こる感情にずっとやられてきたので。辛いけど、悲しいけど“でも”っていう先をやりたいな、って。常に」
――色んな感情を認めるし、受け止めるし、どんな感情を持つことも許される、という。
「そう。音楽としても人としても、そういう存在でありたいですね。アーティストって偶像性が高いものだから。芸能人もそうだけど、いるんだけどいない、みたいな感覚。俺はそういう存在に希望を持っているんです。確信が持てないことが一番の希望になるから。『情景』という空想の話を作ったこともそれに近いかな」
phrase03:終わりゆくものに魅入られて

――確定事項じゃないからこそ、託せる思いがある、と。
「「さよならのあとで」という曲があるんですけど、あれは恋人を殺した男の歌なんです。僕は昔、人を殺したいという思いがあって。家族や恋人……大切な人を殺して、それを見て泣くっていうのに憧れていた時があったんです。取り返しのつかないことをやって、それを感じてむなしくなることまでが夢、みたいな」
――その願望も空想だから許される。
「そうなんですよ。変な話、夢の中だったら何回でも人を殺していいし、夢の中では悪いことを何度もしたことがあるから。現実ではしないですけどね」
――でもあくまで夢の中だから、覚めたら終わりますもんね。
「そうなんです、終わるんです」
――だからこの間の『情景』のステージも本編で空想の世界は終わって、アンコールからは現実世界になっていた。終わるところまでみせることで、いわば「夢オチ」にしているのかかなって。
「そう、夢オチです!本編が終わって全員でお辞儀をしてから“終わり!”ってしたと思うんですけど、そこを明確にするのが大事で」
――朝起きて夢が覚めた、みたいな。
「そうそうそう。人死んでないし世界終わってないし、大丈夫。顔あげなよって。これが現実だよって。アンコールでフリースタイルを始める前にぐだぐだトークをしたのも、みんなでゆっくりと現実に戻ってくるような時間にしたかったからなんです」
――空想が解ける瞬間までがあの物語なんですよね、やっぱり。
「人生で一番楽しい瞬間って何かが終わる時なのかなって。だから、人が死ぬのがすごく好きなんですよ。悲しいんですけど……。僕は中学生の頃ラップの友達が死んでいて。彼は高校生だったんですよね。病院に入院しているのは知っていたんですけど、一時退院した時にも朝から電話来て“GOMESSなにやってるの?フリースタイルしようぜ”って電話越にラップしちゃう、みたいな人で。俺が初めてライヴをしているのを観たラッパーだし、初めてカラオケに連れてってくれた友達だし……すごく大事な人だったんですよね。……なのに急に死んじゃって。すごく落ち込んだんですけど、その時のことを今になって思い出してみると、凄く大切な出来事だったなって。死を、ポジティブな意味で捉えています。悲しかったなって、それも含めて」
――喪失がもたらす感情の動きに、魅了されるということでしょうか?
「死んで良かったということじゃないんだけど。でも、言い換えればそうかもしれないし。生まれる時だって生まれたから嬉しいんじゃなくてもっと理由がはっきりある。この人の子供だから嬉しいとか。この人の子供だから生まれてほしくないとかもある訳だから」
――つまりは命そのものが持っているエネルギー自体に魅かれるんですか?
「そう。なんかね、パワーがすごいんですよ。終わって失って増えるって、面白く無いですか?中でも死っていうのは爆発力がありますよね。それに生まれるのに関わる人数より、死に関わる人数の方が多いから。生きた年月が長いほど多くなるからね。小さい頃から何の漫画を観ても映画を観ても、人が死ぬシーンですごく感動する」
――やっぱりそこに心を動かされるんですね。
「だから自分の物語の中でも人を死なせがちなんです。この人、ここで死んだら美しいな、みたいな。あとは自分の死期にもこだわりたいですね。でも自殺はしないって決めてるから、偶然死ぬ必要があるので、その時のために頑張って不健康な生活をしてみるとか……」
―――いやいやいや……。
「まあ、でも自分の死は見たいですね。当然悲しんでいる人とかを見るのはつらいとは思うんですけど。つまるところ、僕は世界で最後のひとりになりたいんですよ。全員がいなくなった世界を観たい」
――GOMESSさんは全ての物事の“終わり”を見届けたいんですね。
「そう、地球が終わるところとかも観たいんですよ。悲しいだろうし、すごく寂しいだろうし、めちゃくちゃ苦しいんだろうけど、それを受け入れてでも最後の一人になりたいんですよね」
――でも、当然のことながら全ての終わりを見届けることは不可能なわけで。
「そう。だからアーティストの偶像性じゃないけど、確信が持てないことが一番の希望になるから」
――あるかもしれない、と信じられることが希望だということですか。
「たとえば来月大好きなアーティストが来日するという予定があったとして。それは正直確信のように思っているけど、来日中止とか病気するかもしれないし、決まりきってないじゃないですか。その99%くらいでおさまる希望みたいなものをいつも作っていたいし、そういうものを感じていたい。分からないものが一番嬉しいなって思います。今見えている現実はたいがいもうあるから。そこにないものを作っていきたいですね」
GOMESS BAND http://www.gomeban.com/」
■monthly Rock ‘n’ Roll vol.2 ――THE BACK HORN 「未来」
取材時、普段はロックンロールばかり聴いていると言った私に「どんなバンドを聴いてるんですか?」とGOMESSさん。いくつかのバンド名を挙げた中で、彼も好きだと言ってくれたのがTHE BACKHORN。「宇多田ヒカルとのコラボ曲は、どうでしたか?」なんて逆に質問される場面も。その時にも少し話したのだけれど、GOMESSさんの楽曲とTHE BACKHORNにはちょっと共通している部分がある。それは曲に強い生死観が反映されていること。「未来」を選んだのは、しんとしたサウンドと、喪失が纏わりついた世界から歌と共に未来へと歩み出す詞が、今回のインタビューとリンクしたから。
 イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。「音小屋」卒。鹿野淳氏、柴那典氏に師事。守りたいのはロックンロールとロン毛。今月の『音楽と人』はThe Birthdayに9mm、イエモンのエマさんのbrainchild’sそして怒髪天までもいる激渋ロック祭り。レビュー陣の中では若手ですが、ラインナップの渋さとゴツさだけは大御所の方々にも負けていません……! たぶん。
イシハラマイ●会社員兼音楽ライター。「音小屋」卒。鹿野淳氏、柴那典氏に師事。守りたいのはロックンロールとロン毛。今月の『音楽と人』はThe Birthdayに9mm、イエモンのエマさんのbrainchild’sそして怒髪天までもいる激渋ロック祭り。レビュー陣の中では若手ですが、ラインナップの渋さとゴツさだけは大御所の方々にも負けていません……! たぶん。