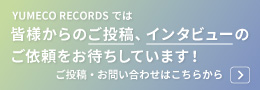だって、メンバーがTwitterでも始めて自らファンに歩み寄れば、宣伝活動はもっと上手くいくでしょう?
だって、わかりやすく「君」や「愛」や「希望」を唄えば、もっと大勢の人にストレートに響くでしょう?
みんなそうやって、成功へのカギを握ろうと努力してるじゃん。
どうしてそうしないの。
――このタイミングでライヴを見て、改めてその答えがわかった気がしている。それは、彼らが「自身の音楽」というフィールドの上「だけで」ひたすらに戦おうとしている、ということだ。彼らはそこで不器用にも見えるほど我武者羅に、なにかを伝えようとしている。響かせようとしている。素っ裸でもがいている。
東京公演1日目。始まるや否や、「ぶっ飛ばす系の曲たちをぶっ続けで」演奏し始めるものだから驚いた。“THE BUNGY”。裏打ちの利いたロカビリー風味漂うノリの良いナンバーであり、08年のリリース以来フェスの盛り上がりポイントでも欠かせない1曲となっている。しかし、まさか1曲目に持ってくるとはだれも思わなかったであろう。お陰でこの日のフロアは初っ端から非常にアツかった。ステージ上のメンバーも、1曲目とは思い難い程に額や首筋をきらきらさせている。
「ライヴ版ノンストップ・メガミックス」と銘打って、この“THE BUNGY”から“風人”、“チェインリアクション”、“妄想隊員A”をバスドラの4つ打ちで器用に繋げて披露する。サウンドの力強さと安定感はこれまで以上だ。序盤早々、NICOが一層タフになっていることがわかる。
「アタマから飛ばしすぎたかな?今回はシングルもアルバムも関係なく俺らが今聴いてほしい曲をとにかく演奏するツアーです。ついて来られますか東京!」
そう述べた光村龍哉(Vo&Gt)の切れの良いストロークで始まったのは“速度”だった。思わぬレアな選曲に、オーディエンスから歓喜の声が上がる。シンコペーションを多用したメロディラインとベースラインが互いに唄い、そして絡み合うサウンド。NICOらしい、一筋縄では行かないアンサンブルに思わず溜息が出る。続く“image training”はファンの新旧を問わず人気のナンバー。余裕を除かせながら笑顔で演奏するメンバーに、曲中でも思わず拍手したくなる。気づけば、もう8年近く彼らはこの曲とともに在るのだ。
そして、「日本語で歌ってここまでカッコいいロックナンバーが他にあるか?」と個人的には思ってしまうほどの楽曲、“SIMON SAID”が披露された。フレーズに間(ま)を多用しつつも重厚に響かされるグルーヴィなサウンドはヒリヒリとした緊張感を誘い、アイロニカルな言葉はリスナーの心をグサグサと突き刺してくる。対馬祥太郎(Dr)の、絶妙なタイミングで鳴らされる跳ねたドラミングもこの曲の肝だ。思わず息を止めてしまった<アタシは犠牲者さ>という終盤のフレーズが痛いほどに響き渡ると、このギリギリ感そのままに“アビダルマ”へ。イントロの坂倉心悟(Ba)のスラップがとにかく格好良い!この曲で序盤の盛り上がりに負けないほどアツさを取り戻したかと思えば、今度は古村大介(Gt)がマイクの前でシェイカーを振り始める。それに合わせ、アフリカの大地に来たのかとでも言わせんばかりの重たいコーラスとフロアタムの音色が響く。再び静まった会場に鳴るのは、そう、“鼓動”だ。<ただ走れ 目を血走らして>というフレーズが、昨年のリリース時よりもよりダイレクトに、そしてリアルに響いたのは、彼らが並々ならぬ想いを携えて控えている今年8月の武道館公演のことが私の頭にあったからなのだろうか。
ちょっとエスニックな要素のある“鼓動”に続いたのは、こちらもまたラテンっぽいリズムワークの“プレイヤ”。この曲が、この日一番の美しさと妖艶さを放っていたに違いない。静かなサウンドの中に狂気や情熱が時折見え隠れし、そして終盤に近づくに連れて厚くなるアンサンブルの中で徐々に溢れ出していく。光村の歌声が本来的に持つ色気、間奏に作られた僅かな溜め(これも間(ま)と呼ぶべきだろうか)、そこに生まれる緊迫した空気、どれをとっても本当に美しかった。
そしてさらに特筆すべきは“夏の大三角形”だろう。これまでのライヴに比べ最も生まれ変わったのはこの曲だ。ライヴで聴いたことのある方ならわかるかもしれないが、以前、恐らく彼らはこの曲で同期演奏(生音以外の音を演奏に合わせて鳴らすこと)を利用していた。CD音源ではギターがダブルリードであったりオケの弦楽隊のピチカート音が入っていたりと非常に凝ったアレンジであったため、ライヴでこの豊かなサウンドを再現するのが大変困難であったからだと思う。しかしこの日は、明らかに4人だけの音でこの曲を鳴らしていた。音数がぐっと減ってシンプルなアレンジになっていたのだけれど、それが本当に素晴らしくて思わず涙が出そうになった。今のNICOのモードが投影された、「すっぴん」な“夏の大三角形”。シンプルであるものを魅力的に見せるのはきっと難しい。きっとこれも彼らの自信と覚悟の表れなのだと思い、天井のミラーボールが放つ無数の星のような光の中で胸が熱くなった。ただのラヴソングなんかじゃない。
さて、これほど濃厚なライヴをしていながらまだまだ中盤。「大会場でやるのは初めて。きっとみんな知らないと思います。」なんてはにかみながらこっそり予防線を張る光村がアコギ1本抱えて弾き語りだしたのは、インディーズ時代の名曲“僕がいなくても地球はまわってる”。イントロが始まるや否やあちこちから息を吞む音が聴こえた。光村の発言は杞憂だったというわけだ。ファンはちゃんと聴いている。
10代で書いたとは到底思えない渋いメロディライン、しかしそこに乗るのは青く棘のある言葉の数々。NICOのどの曲にも何らかの形で描かれている「孤独」な感情がこの曲ではとりわけ全面に押し出されており、胸をぐりぐりと抉ってくる。後半、ほかの3人も加わってからの演奏はさらにエモーショナルだった。古村が時折差し込むギターのフレーズがなんともブルージーで切ない。
しっかりと聴かせた後は、再びアッパーなロックチューンに戻っていく。まるでローラーコースターのようなセットリストだ。坂倉の力強くうねるようなベースラインが一際輝き、対馬の勢いがありつつもしっかりフロントを支えて舵を取るドラムスが映える3曲、“錆びてきた”、“衝突”、“GANIMATA GIRL”だ。途中で花火が弾ける演出もあったし、オーディエンスもちゃんとNICOのコースターに乗っかってまたヒートアップする。ギターがぎゃんぎゃんと鳴り響くようなナンバーでもどこか繊細さが見えるような絶妙なバランス感があり、また如何なるときも愁いを帯びることを忘れない光村の声がNICOの楽曲に独特な多面性を生み出している。音楽が、非常に人間っぽい表情をしている。これぞNICOの楽曲の魅力だと、改めて実感する。
続く“バニーガールとダニーボーイ”では光村がC&Rを取る。みんな本当に楽しそう。ステージから放たれる熱気に、オーディエンスも夢中で返答していた。曲中、歌詞に合わせて「本当は、東京のここにいる全員の手を握っていたい気持ちでいることを……ここに告げておきます」と囁いた光村。会場中から拍手が起こる。みんな必死で握り返したい想いでいっぱいなのだ。
ノリノリのまま次に披露されたのは、高揚感のあるギターアンサンブルを冒頭に添えて始まった“ニワカ雨ニモマ負ケズ”、そして汗だくの笑顔で光村が告げた「東京の皆さん!皆さんのケツに鞭打っていいですか!」という言葉と、勢いのある古村のタッピングで駆け出した“ローハイド”。双方ともに音源とは違い、よりダイナミックでごつごつとした音作りであるな、という印象だ。この2曲、NICOの楽曲の中ではテンポが速いほうであるが、昨今主流のロックチューンに比べれば恐らくやや遅めである。しかしBPMだけでは表現しきれない勢いの良さや空間的な広がり、そういった曲における漠然としたイメージや印象を、このバンドは音色そのもので表現している。凄い。そんな感覚を抱くとともに、気づけば本編が終了していた。
アンコールに応え、再びすぐにステージに姿を見せたメンバー。「アンコールありがとうございます!2014年、最強のダンスミュージックが出来ました。聴いてもらえますか。 “天地ガエシ”!」
待ってました、と言わんばかりに盛り上がるオーディエンス。そう、今年6月11日にリリースされたばかりの新曲が、この“天地ガエシ”だ。アイリッシュでゴキゲンなエレキギターのイントロは、フィドルなんかで演奏しても違和感がなさそうなフレーズ。NICOの楽曲には珍しく表拍でタテにリズムを刻みながら、4人ともきらきらとした笑顔で演奏している。光村が得意とするちょっと切なげなメロディラインの唄が入ると、<孤独なフィールドの上>という言葉が、自身の音楽ただそれだけで勝負しようとしているNICOそのものに重なってぐっと胸が締め付けられてしまう――ただしこの曲、冒頭の軽妙だが穏やかなアイリッシュ風イントロからは想像もつかない、とんでもなくハッピーな仕掛けを持っているのである。そう、(前述したこととは逆になるが)テンポアップだ。より解放感のあるテンポ感の中、じゃじゃ馬のように古村がソロを弾く。オーディエンスもノリに任せてとにかく踊る。会場全体が底抜けに明るいサウンドに思いっきり笑い、一方で不器用なまでに叫ばれる<リベンジ>――NICOは今年8月に控える自身2度目の武道館公演をリベンジと捉えている――に涙し、双方の感情が交差する瞬間を心から楽しんでいた。ちょっとばかり不思議で、しかし温かい光景だった。
ラストは、ライヴでお馴染み“手をたたけ”。ファンやメディアの間でも様々に議論がなされたこの曲であるが、今はただただ楽しい。光村がラストサビの一節でオーディエンスにマイクを向け、フロアは大合唱。私も一緒になって大きな声を出そうとするが、<消えない痛みを抱えたとしたって>というフレーズを唄ってみてハッとする。そこに描かれるのは、永久に癒えることのない痛みや悲しみを受容し、認め、そしてそれでもなお前を向こうとする強さだ。3000人の声が紡ぐこのフレーズがステージ上のメンバーに一心不乱に降り注ぎ、彼らの姿にぴったりと重なったように思えた。
「俺らバンド名はすましてるけど、本当はこの幕(ニコタッチズザウォールズ、とカタカナで書かれた毛筆のような書体のロゴ)みたいにさ、不器用で不恰好で泥臭いバンドなんだってことを出していかないと、って。」
「今日は本当にどうもありがとう!8月19日、武道館で待ってます」
大きな声ではっきりとそう述べて、深いお辞儀を何度も何度もしてからメンバーは袖に消えていった。空っぽになったステージをいつまでも見上げているオーディエンスの心には、ライヴが終わってしまったことへの寂しさや虚しさよりも、もっと温かく、そして強い確信の気持ちがあったと思う――NICO、凄い。NICOの音楽が持つパワーは途方もない。今の彼らなら、武道館は絶対に素晴らしいステージになる――あの日居合わせた誰もが、そう感じたのではないだろうか。
冒頭でも触れたが、現在NICOは、昨今珍しくメンバーのうち誰ひとりとして公式なTwitterのアカウントを所持していない。故に、ある意味ファンとの交流が行われる場所はほぼライヴのみであると言って良いと思う。それからNICOの楽曲は、どれだけテーマがはっきりしていたりシンプルな言葉を遣っていたりしたとしても、一面のみから物事を捉えた単純明快な曲はただの一つとして存在しない。いつもよく聴くと多面的で、どこかしらに憂いを帯びていて、だから綺麗な嘘をつくこともできなくて、ほんとうに人間くさい。きっとこういう曲の真意が多くの人に伝わるのには時間がかかる。ならばもっと単純に、響きのいい言葉を連ねて唄えばいい、という話なのかもしれない。けれどNICOはそうしない。NICOのやり方を変えることはない。
NICOは昔からずっと、彼らの信じた音楽、すなわちNICO自身の音楽ただそれだけで、ひたすらに想いを伝えようとしている。そしてそれが伝わったとき、またはリスナーとしてそれを受け取ったとき、そこに生まれる感動やエネルギーがいかに大きく素晴らしいものなのか、それをこのライヴで確かに皆が実感し共有した。
この多様な音楽が溢れる時代で、こんなプリミティブなやり方。だからこそ伝えるのには時間がかかるかもしれない。難しいことかもしれない。回り道に見えるかもしれない……けれどその回り道は、彼らの音楽に向ける情熱のように、「何よりもそして何処までも真っ直ぐである」という素敵な矛盾を孕んでいる。
どうかこのすっぴんなNICOのライヴをあなたにも目撃してほしい。どうかNICOの武道館公演が大成功してほしい。否、必ずするだろう。彼らにはもう、その先までちゃんと見えているのかもしれない。
――それが、たとえ「真っ直ぐな回り道」の続きであったとしても。