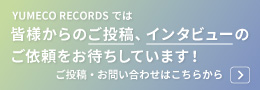最近は、大文字の日本語表記のバンド名が多く、それぞれ面白く、これからもより増えていきそうですが、その新進の中でも、何かしら浮いた存在、バンド名と独自の音楽性を磨き上げているひとつにチェコ・ノー・リパブリック(Czecho No Republic)はあるかもしれません。
なお、附箋としまして、国としてのチェコ共和国の綴りは“Czech Republic”。ボーカル、ベース、メインソングライターの武井優心氏はインタビューでそれと違うので、「No」を付けたというとおり、捻じれた始まりがあり、その捻じれた始まりは2010年3月に結成されたときから、日本の邦楽シーンと一線を隔しまして、ブルックリン・シーンと言われましたUSインディーの音楽要素を含んでいたところにも準拠いたします。
MGMT、ヴァンパイア・ウィークエンド、YEASAYERなど、彼らはアート・センスと過去の音楽遺産の巧みな捌き方と言いましょうか、その現代的な絶妙な距離感と対象知性で人気を博していき、今や世界でも欠かせない存在になっているバンドも少なくなく居ます。ブルックリン・シーンと呼ばれるベースを支えていましたものは機知(既知)とリリシズムと集約されるといえるかもしれず、主にユースのスケープゴートとして扱われがちなロック/ポップスという音楽を逆手に玩具箱をひっくり返したような多彩な音を届け、みんなで楽しめたらいいというものでもあり、それは動画で共有配信できますポスト・インターネット時代に於いての仮想的な繋がりもありましたが、チルウェイヴなどとは違い、もう少し現場主義的な積み重ねもあります。現に、当初はハイプ的に思われておりましたバンドがライヴ・パフォーマンスを重ねるにつれ、今やしっかりとした作品とともに10年代をサヴァイヴしていこうとしていこうとする趨勢も出来ています。
ただし、シーン(後景)と括られるものは移りゆくもので、ブルックリン・シーンというものも恣意性を孕んでいたとしましたら、日本で重要なものはそのバンド由来、アーティストそのものが持つナラティヴ、内面的な鏡像性が重視されてきたところは否めません。今年、戻ってきましたサザン・オール・スターズや、スピッツといったベテラン・バンドには多くの作品の裏に多くの物語性や精神論が付与します。
そんな中で、10年代はザッピング性が高まり、受け手側の単曲買いから、発信サイドのフェス・バブルなどの様相が強まり、更には個々アーティストも多種多様な配信方法を取るようになり、例えば、そのアーティストがもはや“歌っていなくもいい”という倒錯も生まれ得ています。アイドル・グループの乱立はまた、別枠の話になりますので、留保しておきますが、みんなで聴ける歌、というのは共有ではなく、閉じた共同体、または、加工された二次過程の後に成り立つという隠喩をしてみても不思議ではないかもしれません。
チェコ・ノー・リパブリックは当初から、そんな時代背景と無縁にといいましょうか、カラフルなポップネスを追求する姿勢と、一聴だけでは過ぎてしまうような軽やかさを持って出てきました。ファースト・アルバムの『Maminka』は2011年10月にリリースされていますが、若手バンドの作品としては異端なものを感じました。それは、刹那性と煌めきが凝縮されていながらも、能天気なパーティーへの招待状のようなもので、また、パーティーの開催場所が「Don’t Cry Forest Boy」のMVに見受けられますように、のちに「Ivory」という曲でもあらわれますように、フォークロワ的な神話性があったことです。
フォークロワ的な神話性を2011年の時点でそれこそ震災が起こり、なにかと文化的な閉塞が強まっている状況で音楽として表象することの難しさは想像するだに余りあります。ゆえに、『Maminka』には七色のパレード、僕のシャツの柄、ジョンレノン、親の涙などのフレーズがこんがりながら、未来の側に視線を向けようとするほのかな明るさが前景しています。悲観や暗がりを装うのは平易な中で、シンセが活き、楽しそうに演奏をしますメンバーのスタイリッシュな姿は私には少なくとも頼もしく映りましたし、その『Maminka』は、CDショップ大賞にノミネートされるなど耳の肥えたリスナー、評論家のみならず、一部のユースにも届いたものの、大多数に受け入れられたという訳ではありませんでした。
セカンド・ミニ・アルバム『Dinosaur』ではよりファンタジーとリアリティーの狭間で、移動式遊園地みたいな、と当時、彼らが称していました音が響いています。1曲目、「1、2、3、4」の合図が入り、皆で「ダイナソー」と歌う彼らは浮いているといえば、浮いていましたが、聴いていますと、持っていかれる目映さがあります。サイケデリックでユーフォリックにネジが少し外れたかのようなサウンドに、ダイナソー、つまりは、恐竜のように強くなりたいと言いながらも、春夏秋冬を巡る繊細な物語風の歌詞世界、更にはカーニバルの始まりに飛び込もうとするカオティックな内容。
バンドという有機体もライヴ活動とともに、移動したら、そこは離れ、どこかへ行きます。ただ、どこかにそこがなり、そこがまた、どこかへ、最後はここに戻ってこられたらいいのかもしれませんが、日常はハレだけでもケだけでも成立し得ません。そう思いますと、チェコ・ノー・リパブリックというバンドは当初から、漂うように「日常」を見詰め続け、その結果としてか、メンバーや音楽性が変わっていきました。
現メンバーはボーカル・ベースの武井優心氏、ドラムスの山崎正太郎氏という初期メンバーに、2011年2月から加入しましたギターの八木類氏、2013年1月から加入しましたモデル活動もされていますボーカル、コーラス、パーカッションのタカハシマイさん、ギターの砂川一黄氏の五人体制になっています。
その体制になり、ヴィジュアル面での鮮やかさと曲調のユーフォリアをして、煌めき、スタイリッシュなイメージが再度ついていますが、チェコ・ノー・リパブリックというバンド名を掲げ、このたび、メジャー・デビューアルバムとして『NEVERLAND』を上梓しました。
ネバーランド——有名映画や亡きマイケル・ジャクソンの夢の象徴を想い出す人も多いでしょう。
しかし、砂漠におけるオアシスを求める、放浪者のような、または、安部公房氏の小説「砂の女」のような井の中の蛙的に空を見上げて、どうにもならない狭い箱庭の中で、ありったけの音楽語彙の多岐性を投げる、そんなところを全体から感じます。終わりの始まり、始まりの続き、ということ。
『NEVERLAND』では、過去曲と新曲を合わせた形で、残像に虚無が残りながらも、今夏を彩りました「Festival」というシンボリックなものを経ての“果て”をこの作品で始めようとしています。
つまり、始まりから“果て”から未来を巻き戻そうとする行為性の美しさ。今作では、冒頭から、ネバーランド、という有り得ない概念を彼ららしいドリーミー・ポップ、掛け声とともに創成しようとするさまはいつかのスピッツの「ロビンソン」のような切なさと、誰も触れない二人だけの国への夢想への距離を駆け抜けます。この、難渋な2013年の今に。
ネバーランド 幻想のランド
ネバーランド ある訳ない
(「ネバーランド」)
両義撞着に引き裂かれながら、イマジネーションの奔流へとネバーランドの断片を繋げ、そこに、いしわたり淳治氏がサウンド・アンド・ワーズにおいてプロデュースで参加しました武井氏の作詞・作曲の「MUSIC」がなだれ込みます。
現代音楽家のジョン・ケージ的に、音楽は人を救うのか、または、空気を揺らすだけなのか、そういった愚問を解消するようなミニマルなリズムの反復とタカハシマイさんのコーラスが心地良い新機軸ともいえる曲です。ただ、ここでも、「三途の河で足湯して 菩提樹の下で一眠り」なんてフレーズが挟まれ、死、虚無が霞みますゆえに、軽やかなハミングの間に光が差します。それは、今回、プロデュースで参加しています片寄明人氏のGREAT3がタイムレスに、多くの影響を与えます幾つかの曲群がそうだった印象を想い出せば早いように。
過去からの曲では、もはや、ライヴでも定番の「Call Her」、「レインボー」はアップデイトした名刺代わりの彼らの名前を新しい未だ視ぬ聴衆に届けるようなポップ・ソングとして機能、再写化しています。
ふと、ここで想像してみますのは、彼らはまずは邦楽というある種の共通言語内の狭いムラで“新しいバンド像”を作っていく可能性があるのではないか、ということで、それは、例えば、乱立しますカテゴライズ内の一アクトとして演じるのではなく、チェコ・ノー・リパブリックという孤島か砂漠でもいい、そこに国旗に掲げても、パレードを起こせるのではないか、そんな彩りの縁をなぞります。だから、アルバムの中心部には前述しました「Don’t Cry Forest Boy」が片寄明人氏のプロデュースの下で、カンタベリー的なソフト・ロックの残響内で組成し、森の中での神話に仮託する様がよぎります。そして、放浪としての旅へと向かう「トリッパー」は骨頂ともいえるでしょうか。そのまま、9曲目の「幽霊船」でハイライトを迎えるような感覚を受けます。
震えるリズムとシンセの響き、爽涼過ぎた過去のヴァージョンから少し腰を落ち着けた空気感に、今の彼らの気概が滲みます。
彼らが乗り込むのは難破船でも優雅な客船でもなく、幽霊船であり、その幽霊船を捉え直すべきはこれまでの彼らを知ってきた人たちばかりでないはずで、これからの人たちに向けての残映ではないか、とも思います。その幽霊船を、対象化して境目を描く11曲目「国境」は不思議な浮遊感とTweet(独白)的な歌詞が残る佳曲になっているのも“続き”を感じます。
あぁ まだ どうか 死なないで
あぁ まだ 二人で じゃれたいよ
(「国境」)
最終曲「エターナル」では寂寥を感じながら、未来に対してせめて、手を伸ばそうとするが、その未来が今日、明日、二年後、五年後の積み重ねなのを知りながら、わからないと言及していますが、このアルバムを経まして、彼らの確かな足取りの揺らぎ―あえての語義矛盾ですが、言い切ることが正しいような瀬で言い切れない誠実さのひとつの結実の途中過程を感じます。
あの箱舟 いつ見たって未完成だから
もう乗れなくてもいいんだよ
(「Don’t Cry , Forest Boy」)
どんな形にしましても、もしも、どこかから誘いを受けました何らかの箱舟に乗る意思がないとしましても、未来的な何かを掴むべく、チェコ・ノー・リパブリックというバンドはその名前どおり、新しいバンド像と続きを描こうとしている、そんな想いがあります。せめて、そんな想いと音楽の余韻がこの文章の中から響けば、幸いです。
まつうら・さとる●1979年生、個人的に山場、変化のための準備といえる出来事が今年は一気に多く訪れ、愉しいこともしんどいことも尽きませんでしたが、あと数ヶ月、忘年会や鍋を囲みながら、ゆっくり振り返れたらいいな、と想うこの頃です。色んな人に助けられ、感謝も尽きません。今は、12月に来日しますファナ・モリ―ナが楽しみです。